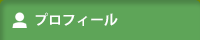昨日の晩は自分の部屋に携帯を置いたまま風間さんの家に避難しちゃったから連絡がつかないのも当然だ。
とは言え正直にそんなことを言うわけにもいかないから適当な言。
でも、そんな私の発言に左之は全く怒っている様子も無い。
それを見たらちょっと胸が痛んだけど、彼はただ純粋に私を心配してくれているのだと思えば私の自尊心はこれでもかと満たされた。
それで家まで訪ねてきちゃうなんて、ほんと私にベタ惚れなんだから。
カワイイね左之って。
「そういやその指・・・怪我でもしたのか?」
「へ?」
言われて私は包帯の巻かれた自分の指先に視線を落とす。
そうだ、昨日お茶を入れようと思って指を火傷したんだったっけ・・・。
「ああ、これね。家でお茶を入れようと思って火傷しちゃったの」
「大丈夫なのか?」
「うん、大丈夫よ。風間さんが手当てしてくれて・・・」
そこまで言ってハッと口を噤む。
・・・まずい。
「ん?風間さんが?」
「い、いや、違うの、自分で手当てしたんだけど、その、風間さんにドジだなって笑われて・・・ははっ」
何言ってんだ私。
家に風間さんを入れてるなんてバレたらヤバいでしょ!
でも、私のしどろもどろの言い訳に左之は一瞬妙な間をおいてから「そうか」と言っただけだった。
「しかし風間さんとお前の部屋が隣同士だったとはな・・・。それで朝から晩まで一緒に仕事してたら一日のほとんどをあの人と一緒に過ごしてる感じじゃねえか?」
「ええ、まぁ・・・ね」
「仕事とはいえ、それってどうなんだ?そんだけ一緒にいたら俺より風間さんの方が大事になっちまったりしてな。」
「何いってるの、冗談はやめてよ」
くくっと笑いながら探るような目をする左之に、私もぎこちない笑顔を見せながら返事を返す。
もちろんそんなことなどあり得ないと分かっているのに、何故か自分の顔が強張るのを感じた。
「そういやお前、さっき会った時化粧してなかったな。格好もいつもと違ってくだけた感じでよ」
「あ、いや・・・あれは、」
「初めて見た気がするぜ、あんな風に気を抜いたお前の姿」
「えっと、あの時はたまたま・・・。でも左之にはあんな姿なんて見せたくなかったな」
私は頬をひきつらせながら無理に笑って見せる。
あれを見られたのは一生の不覚だった。
大体すっぴんで会って私だと気づいてもらえただけでも奇跡かもしれない・・・ってほっとけよ。