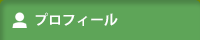ワイルダンターのレルドリンは十八歳だったが、無邪気な性格のおかげで子供っぽく見えた。どんな感情で公開大學 課程もかれは少しもためらうことなく表にあらわし、おかげで率直さがあたかも
かがり火のごとく顔に輝いていた。かれは感情にかられやすく、大仰なもの言いをし、ガリオンは認めたくはなかったのだが、どうやらレルドリンはさほど利口とはいえなかった。そ

れでも、ガリオンはかれを好きにならずにはいられなかった。
翌朝、ガリオンがマントを着てひきつづきヘターを待ちに出かけようとすると、レルドリンがすかさずついてきた。レルドリンはけばけばしい服を着替え、今は茶色のズボンと緑の
チュニック、それに濃い茶色の毛織りケープという恰好をし公開大學 課程ている。弓を持ち、ベルトには矢筒をたずさえ、雪の中をくずれた西門に向かって歩きながら、前方の半分ぐらいしか見え
ない的に矢を命中させては、自分で驚いている。
「きみはものすごく腕がいいんだね」ガリオンはほんとうに見事な一撃のあとで、感心して言った。
「アストゥリア人だからな」レルド公開大學 課程リンは謙虚に言った。「ぼくらはもう何千年も弓を引いてるんだ。親父《おやじ》はぼくが生まれたその日にこの弓のリムを切らせたんだけど、八
歳になるころにはもう引けるようになってたよ」
「きっとたくさん狩りをしただろうね」ガリオンはあたりのうっそうとした森や、雪の中で見た獲物の足跡のことを思いながら言った。
「狩りはぼくらのもっとも一般的な娯楽だからな」レルドリンは立ち止まって、木の幹から今しがた射ったばかりの矢を引き抜いた。「親父は食卓に牛肉や羊肉がのらないのをひそか
に自慢してるんだ」
「一度チェレクで狩りをしたことがあるよ」
「鹿かい?」レルドリンは聞いた。
「ううん、野生の猪さ。でも弓は使わなかったな。チェレク人は槍で狩りをするんだ」
「槍だって? 槍なんかで何かを殺せるくらいまで近づけるのかい?」
ガリオンはあばら骨の打撲と頭痛のことを思い出して、ちょっぴり悲しそうに笑った。「近づくことはそれほどたいへんじゃない。難しいのは、槍で突いたあと逃げることなんだ」
レルドリンはよくわからない、といった顔をしている。
「まず猟師が隊列を組むんだ」ガリオンは説明した。「そして、できるだけ騒々しい音をたてながら、森の中を突っ走っていく。きみは槍を持って、騒音から逃れようとする猪が通り
そうな場所で待ってるんだ。猪は追いかけられて気がたってるから、きみを見るなり突進してくる。その時さ、きみが槍で突くのは」
「危なくないのかい?」レルドリンは目をまるくして聞いた。
ガリオンはうなずくと、「ぼくはもうすこしであばら骨をぜんぶ折るところだったよ」かれは自慢しているつもりはまったくなかったが、実は、レルドリンが自分の話に反応してく
れたことがうれしかった。
「アストゥリアには獰猛な獣はそう多くないんだ」た。「熊がすこしと、時たま狼の群れがいるくらいだな」かれはちょっとのあいだ口ごもっていたが、
やがてまじまじとガリオンの顔を見た。そして意味ありげに横目でかれを見ながら、「でも、中には野生の動物よりもっと面白い獲物を見つける人間がいるんだ」と言った。
「えっ?」ガリオンはなんのことだかよくわからなかった。
「アストゥリア内にミンブレイト人が多すぎる、と考えている者がいるんだ」レルドリンは重重しくアクセントをつけて説明した。
「アレンド人の内戦はもう終わったのかと思ってたよ」
「そう思っていない人間も大勢いるのさ。アストゥリアがミンブレイト王室の支配を離れるまで戦争はつづくと思ってる人間がね」レルドリンがどちらの意見に立っているのかはその
声を聞けばすぐにわかった。
「この国は〈ボー?ミンブルの戦い〉のあと統一されたんじゃなかったの?」
「統一だって? そんなこと誰が信じるもんか。アストゥリアは属国のように扱われてるんだぞ。王宮はボー?ミンブルにあって、王国内の知事も、収税吏も、執行吏も、長官も、みん
なミンブレイト人なんだ。権力のある地位についているアストゥリア人は、アレンディア中にただのひとりもいない。ミンブレイト人はぼくたちの称号さえ認めようとしない。ぼくの
親父は千年もつづいた血筋の持ち主なのに、地主よばわりされてるんだ。親父を男爵と呼ぶくらいなら、あいつらは舌を噛み切っちまうだろうよ」レルドリンの顔は抑えつけられた憤
りで、蒼白になった。