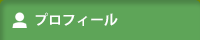「ヘター卿が心優しいわたくしたちの友人を強く叱りすぎたので、彼女は耐えられなくなったのです」アリアナは説明した。「あの方の言葉は、アダーラさまにとって人生よりも大切なんですわ」
「ヘターが」セ?ネドラはあ然とした。
「わたくしたちの友人がヘター殿をどんな目で見つめおられ優思明ていたか、お気づきにならなかったのですか」アリアナは少し驚いたようにきいた。
「ヘターが」セ?ネドラは繰り返した。「知らなかったわ」

「たぶん、それはわたくしがミンブレイト人だからですわ」と、アリアナ。「わたくしたちは、そのような愛情の気配に敏感なのです」
ヘターは百ヤード行ったところで暴れ出したアダーラの馬優悅 避孕に追いついた。かれは彼女の手綱を掴むと、乱暴に引き止め、鋭い口調で叱責した。アダーラは身をよじらせるようにして、彼女を叱りつける顔を見まいとした。
突然、十二フィートも離れた場所で何ものかがセ?ネドラの目をかすめた。だしぬけに、二つの貧相な茂みのかげから、茶色の防水布をかなぐりすてるようにして、鎖かたびらを着たマーゴ人が立ち上がった。その手の弓にはすでに矢がつがえられていた。
マーゴ人が狙いを定めるのを見た。「ヘター!」セ?ネドラは叫んだ。
ヘターはマーゴ人に背を向けていたが、アダーラは無防備なアルガー人の背中が弓で狙われているのを見た。アダーラは無我夢中でヘターの手から自分の手綱を奪い返すと、かれの馬にぶつかって行った。かれの馬は大きく前脚を上げてよろめき、ヘターを振り落としながら倒れた。アダーラは手綱の端で思いっきり馬のわき腹をたたき、マーゴ人の方に向かって突っ込んでいった。
マーゴ人の顔に一瞬のためらいが走っ優思明たが、すぐに娘に向けて矢を放った。
矢がアダーラを射たとき、かなり遠くにいたにもかかわらず、彼女の悲鳴はセ?ネドラの耳をつんざいた。彼女は後になっても恐怖とともにその悲鳴をしばしば思い出した。アダーラは身体を二つに折ると、空いていた手で胸にささった矢を掴んだ。馬は速度を落とすことなくマーゴ人につっ込み、かれを踏みつけた。マーゴ人は脚踏みする馬の下で転げまわった。馬が通り過ぎると、男はよろめきながらたち上がり、刀を抜いた。しかし、すでにヘターがサーベルを抜いていた。刃が陽光にギラギラと輝き、振りおろされた。マーゴ人は倒れる前に一度だけ悲鳴を上げた。
ヘターは血のしたたるサーベルを握ったまま、怒りに駆られながらアダーラのほうに取って返した。「なんて馬鹿なことを」かれはわめいたが、急に息をのんだ。彼女の馬はマーゴ人から数ヤード離れたところに止まっていたが、娘はうなだれるようにして鞍の上に倒れていた。黒髪が青白い顔をヴェールのように覆いながら流れ、その両手は胸のところで押さえつけられていた。娘は、ゆっくりと落ちていった。
ヘターは言葉にならない叫び声を上げると、サーベルを落とし、アダーラのかたわらにかけよった。
「アダーラ!」王女は叫び、両手で顔を覆った。ヘターが矢で射られた娘をそっと抱き起こした。矢は、アダーラの下胸部に突きささり、弱々しい心臓の鼓動とともに上下していた。
二人の傍に走り寄ったとき、ヘターはアダーラを抱きかかえ、傷つき青ざめた顔をじっと見まもっていた。「馬鹿だ」かれはしわがれた声でつぶやいた。「本当に馬鹿だよ」
アリアナは馬が止まるのももどかしく飛びおりると、ヘターの傍に駆けよった。「どうか彼女を動かさないで下さい」彼女は鋭く言った。「矢は肺までたっしています。もし動かしたりすれば、鋭い矢じりが傷を深くし、命とりになります」
「抜いてやってくれ」ヘターは歯をくいしばりながら言った。
「無理ですわ、ヘターさま。矢を抜けばもっと傷が深くなります」
「このような彼女を見るには忍びないのだ」かれは泣き出しそうだった。
「それでは見ないほうがよろしゅうございます」アリアナはアダーラのかたわらにひざをつき、専門家らしい仕種で傷ついた娘ののどに手をあてた。
「死んではいないだろうな」ヘターは懇願するように言った。
アリアナはかぶりを振った。「傷は深いですけれど、心臓はしっかり鼓動しています。即席の担架を急いで作らせて下さい、ヘターさま。友人を要塞に連れて戻り、すぐにレディ?ポルガラの治療を受けさせなければ、わずかに残されている命の火も消えてしまいますわ」
「何か手当はできないのか」かれは恨みがましく言った。
「このような太陽が照りつける荒れ地では無理ですわ、殿下。道具も薬もありませんし、彼女の傷はわたしの手にあまるくらい深いのです。頼みの綱はレディ?ポルガラだけですわ。担架を、どうか、早く!」
ポルガラがアダーラの病室から出てきたのは午後も遅くなってからだった。彼女の瞳には憂うつな表情が浮かび、その視線は石のように固かった。
「彼女はどうですか」ヘターがきいた。かれは何時間も小要塞の主廊下を行ったり来たりしていたが、ときどき立ちどまっては、抑えきれない気持をぶつけるように、むき出しの石壁を拳で乱暴にたたきつけていた。
「少しは良くなったようね」ポルガラは答えた。「峠は越えたけれど、非常に衰弱しているわ。あなたに会いたがっていてよ」
「彼女は、回復するのでしょうね」ヘターは恐る恐るたずねた。
「たぶん――傷が悪化しないかぎりはね。彼女は若いし、傷は見た目ほど深くはなかったから。今は話をしたがるような作用を与えているけれど、あまりしゃべらせてはいけないわ。彼女には休息が必要よ」ポルガラの視線が涙に濡れたセ?ネドラの方に向けられた。「アダーラを見舞ったら、わたしの部屋に来てちょうだい」ポルガラの口調はかたかった。「少し話しあわなければいけないわね」
アダーラの焦げ茶色の髪が陶磁器のようななめらかな顔を囲むようにして、枕の上に広がっていた。顔色は青白く、うっすらとあけられた目に光をたたえ、かれらのあいだをぼんやりとさまよっていた。アリアナは黙って寝台のかたわらに座った。
「具合はどう、アダーラ」セ?ネドラは、病気見舞いをするときに使う、つとめて明るい調子でたずねた。
アダーラはセ?ネドラを見つめ、かすかにほほ笑んだ。
「どこか痛いの」
「いいえ」と、アダーラ。「痛くないわ。でも、頭がふらふらして、変な気分」
「なぜ、あんなことをしたんだ」ヘタ。「何もマーゴ人の正面から突っ込む必要はなかったんだ」
「いつも馬とばかりいらっしゃるんですもの、ヘター卿」アダーラはかれにかすかにほほ笑みかけながら言った。「ご自分と同じ種族のものが何を考えているか、おわかりにならないんだわ」
「どういうことだ」かれはけげんそうだった。
「言葉どおりですわ、ヘター卿。成熟した雌馬が素晴らしい牡馬に惹かれることにたとえれば、わかっていただけるかしら。でもそれが人間に起きたときには、何もおわかりにならないんだわ」彼女は弱々しく咳をした。
「大丈夫か」かれは鋭くきいた。