魔術師ベルガラスは欠点の多い人物だった。肉体労働が好きだったことはいまだかつてただの一度もなく、暗褐色の酒《エール》が好きなことはいささか度をこしていた。ときには真実を意に介さないこともあり、正しい所有権をめぐる一部の細かい問題になると、あっぱれなほど無頓着だった。評判優悅 避孕のいかがわしい女たちも、かれの好色ぶりには尻尾をまき、かれの言葉の選択が物議をかもすことは跡をたたなかった。
女魔術師のポルガラは人間ばなれした意志の持ち主で、腰のすわらぬ父親の品行矯正に数千年をついやしてきたが、めぼしい成功はおさめていなかった。しかし、悲しいほどの見込み薄にもめげずに彼女はがんばっていた。幾世紀にもおよぶ歳月を通じて、彼女はベルガラスの悪癖をくいとめようと敢然と戦っていた。しかしさすがのポルガラも怠惰と身なりにかまわぬ無頓着さの二点については、匙をなげていた。罰あたりな言葉を吐くこと、嘘をつくことについても、しぶしぶ白旗をあげていた。だがたびかさなる敗北にもかかわらず、酒ののみすぎと、盗みと、女遊びの三つに関しては、いまでも鉄の意志をもって抵抗していた。ある個人的理由から、彼女はそれらの問題に戦いをいどむことが義務だと感じていたのである。
ベルガラスが翌年の春まで〈アルダー谷〉の塔に帰るのを延ばしたおかげで、エランドは、ときおり訪れる平穏な生活の余白に侵入してくる父と娘の果てしない、信じがたいほど複雑なこぜりあいを、まぢかに目撃することができた。ものぐさな老人がいずれもなにくわぬ顔で、ポルガラの台所をうろつき、彼女の暖炉からはあたたかさを、彼女の貯蔵庫からはよく冷えた酒をくすねるたびに、ポルガラは舌鋒するどく非難したが、ベルガラスは数世紀の実績を物語るたくみな技術で、のらりくらりとそれをかわした。しかしエランドはそれらの意地悪な言いぐさや、ものやわらかで軽々しい返事の奥にひそむものをちゃんと見抜いていた。ベルガラスと娘が他人には理解できないほどはげしくやりあうのは、ふたりの絆がそれだけ強いからだった。だから一見果てしない争いのようでも、その実、陰には互いへの限りない愛情がひそんでいて、かれらふたりがそれを隠しているだけのことだった。だからといって、ポル優悅 避孕ガラがいまのままのベルガラスに満足しているというわけではなかった。ただ、口で言うほど、父親に失望しているわけではないということなのだ。
ベルガラスが娘夫婦とともにポレドラの小屋で冬をすごしたのにはわけがあった。ポルガラもベルガラスもそのわけを知っていた。ひとこともしゃべったわけではなかったが、この家にまつわる老人の記憶は変えられる必要があると父娘は思っていたのである――消すのは不可能だった。この世のどんな力をもってしても、妻の思い出をベルガラスの頭から消し去ることはできなかったからだ。だが、記憶は多少変える必要があった。この草ぶき屋根の小屋によってよびさまされるものが、帰宅して愛するポレドラの死を知ったあの悲劇の日だけでなく、ここで過ごした幸福な日々ともなるように。
一週間ふりつづいたあたたかい春の雨が雪をとかし、空にふたたび青さがもどると、ついにベルガラスは延期を余儀なくされていた旅に出るしおどきだと決心した。「本当はこれといって急ぐわけではないんだが、ベルディンと双子のところへちょっとよってみたいんだ。そろそろわしの塔もきれいにしたほうがいいだろう。この数百年、うっちゃっておいたからな」
「かまわなければ、わたしたちも一緒に行くわ」ポルガラが申し出た。「なんと言っても、小屋の修繕を手伝ってくれたんですからね――熱心にではなかったにせよ、手伝ったのはたしかだわ。だからわたしたちがおとうさんの塔の掃除を手伝えば、ちょうどおあいこじゃない」
「ありがたいのはやまやまなんだが、ポル」ベルガラスはきっぱりと断わった。「しかしおま優思明えの考える掃除は、わしにはいささか徹底的すぎるような気がするんだ。おまえが掃除すると、あとで必要になったものをほこりの山からほじくりだすはめになる。どこかまんなかあたりにすいた空間があれば、わしにとっては十分きれいな部屋なのさ」
「まあ、おとうさん」ポルは笑った。「あいかわらずだこと」
「あたりまえだ」ベルガラスは静かに朝食を食べているエランドを考え深げにながめた。「しかし、問題がなければ、この子を連れて行こうかと思う」
ポルガラはすばやくベルガラスを見た。
ベルガラスは肩をすくめた。「道中の話し相手になる。景色が変われば、エランドも楽しかろう。それにな、結婚した日からおまえもダーニクもふたりきりになるチャンスがなかったんだ。おくればせのプレゼントだと思ってくれ」
ポルガラは父親を凝視した。「ご親切に、おとうさん」そっけなく言ったかと思うと、急に目つきがなごみ、愛情がその目にあふれた。
ベルガラスは狼狽ぎみに目をそらした。「入用なものがあるか? 塔からもってきてもらいたいものがあるかということだが。ときおりあそこにおいてきた旅行鞄やら箱やらが山のようになっとるぞ」
「まあ、ずいぶん気がきくのね、おとうさん」
「そういうものにふさがれている場所をあけたいのさ」ベルガラスはにやりとした。
「その子をちゃんと見ていてくださるんでしょうね? 塔の中を歩き回りだすと、うわの空になることがあるんだから」
「わしと一緒なら大丈夫だよ、ポル」老人はうけあった。
というわけで、翌朝、ベルガラスは馬にまたがり、ダーニクがエランドを老人のうしろに押し上げた。「二、三週間で連れて帰ってくるよ」ベルガラスは言った。「でなくとも、すくなくとも真夏までには戻る」身をのりだしてダーニクと握手すると、ベルガラスは馬首を南へむけた。
空気はまだ冷たかったが、早春の太陽はまぶしいほどだった。若芽の匂いが空中にただよい、ベルガラスのうしろにゆったりまたがったエランドは、馬が〈谷〉の奥へはいっていくにつれて、アルダーの存在を感じることができた。それは穏やかな、やさしい意識であり、激しい好奇心に支配された意識だった。〈谷〉の中にいると、アルダー神の存在は、あいまいな精神浸透ではなく、ほとんど手でさわれそうなほどくっきりしていた。
冬枯れの高い草むらをふみわけて、馬はゆっくりしたペースで〈谷〉を進んでいった。ひろびろとした広がりに大木が点在していた。木々はてっぺんのこずえを空に突き出し、葉の芽ぶきだした枝の先を広げて、太陽にあたためられた空気のやさしいくちづけをうけようとしていた。
「どうだ、ぼうず?」一リーグあまり乗ったあと、ベルガラスが口をひらいた。
「塔はどこですか?」エランドは礼儀正しくたずねた。
「もうちょっと先だ。塔のことをどうして知った?」
「あなたとポルガラが話していました」
「盗み聞きは非常によくない癖だぞ、エランド」
「あれは内緒の話だったんですか?」
「いや、そうじゃない」
「じゃあ、盗み聞きじゃなかったんだ、そうでしょう?」
ベルガラスはサッとふりかえって、肩ごしにうしろの少年を見た。「おまえみたいな若いものにしては、そいつはずいぶんうまい区別のしかただな。どうしてそう考えた?」
エランドは肩をすくめた。「なんとなく。あれはいつもここであんなふうに草を食べるんですか?」かれは近くで静かに草をはんでいる十二頭あまりの赤褐色のシカを指さした。
「わしの記憶にあるかぎりではそうだな。アルダーの存在には動物たちを友好的にさせるなにかがあるんだ」
かれらは優雅な一対の塔の前をとおりすぎた。ふたつの塔のあいだには、風変わりな空気のように軽い橋が弓なりにかかっていた。ルキラの塔だ、とベルガラスはエランドに教えだ。彼らは双子の魔術師だが、心が緊密につながりすぎているため、おたがいにどうしても相手の言うことを、うしろ半分は横取りせずにはいられなくなる癖があった。しばらくすると、ばら色の水晶でできた精巧な塔があらわれた。それはまるで柔らかに光る空中にうかんだピンクの宝石のように見えた。この塔はせむしのベルディンの塔だとベルガラスは言った。ベルディンは思わず息をのむほどの美しいものを、醜い自分のまわりにはりめぐらしていた。
ようやくかれらはベルガラス自身のずんぐりした、機能的な塔に到着して、馬をおりた。
「さて、ついたぞ。上にのぼろう」
-
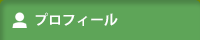
-
-

-

- 未分類 (73)
-

-

-

-



