「なんとも」モリンはためいきをもらした。「世の中も変わったものです。では公式の密偵として陛下にご紹介したほうがよろしいのですか?」
「陛下はすでにお察しだと思いますわ、モリン卿」リセルはかれのやせた手に愛情をこめてふれながら、言った。
モリンは一礼すると、おぼつかない足どりで部屋からゆっくり出ていった。
「なんて感じのいいお年寄りかしら」リセルはつぶやいた。
「これはこれは、いとこよ」シルクは大使に言った。
「やあ」カルドン王子はそっけなく答えた。

「ふたりは血のつながりがあるのかね?」ヴァラナがたずねた。
「遠い親戚ですよ、陛下」シルクが言った。「母親同士がまたいとこなんです――またまたいとこだったかな?」
「またまたいとこのそのまたいとこだよ」カルドンはネズミ顔の親戚をじっと見た。「なんだかみすぼらしいな、おい。最後に会ったときは金やら宝石やらじゃらじゃらつけていたぞ」
「身をやつしているんだよ」シルクはものやわらかに言った。「おまえはおれに気づかないことになってるんだ」
「ああ」カルドンは皇帝のほうを向いた。「われわれの冗談をお許しください、陛下。ここにいるケルダーとわたしは子供のときから互いに毛嫌いしあっていたんです」
シルクはにやにやした。「一目見たときからでしてね。おれたちは徹底的に嫌悪しあってるんですよ」
カルドンはみじかくほほえんだ。「われわれが子供だったとき、双方の家族は家を訪問しあうたびにナイフというナイフを隠したものです」
シルクは好奇心にかられてリセルにたずねた。「トル?ホネスでなにをやっているんだい?」
「秘密よ」
「ヴェルヴェットはボクトールから公文書を数通持ってきたんだ」カルドンが説明した。「それにいくつかの指示を」
「ヴェルヴェット?」
「ばかみたいでしょう?」リセルは笑った。「でもね、もっとひどいあだ名を選んだ可能性もあると思うわ」
「パッと頭に浮かんだものよりましだな」シルクが同意した。
「おじょうずね、ケルダー」
「われわれに知らせるべきだと考えていることがあるようだが、カルドン王子?」。
カルドンはためいきをついた。「悲しいご報告なのですが、高級娼婦のベスラが殺されました、陛下」
「なんだと?」
「昨夜仕事から帰る途中、人気《ひとけ》のない通りで暗殺者一味に襲われたのです。虫の息のまま放置されましたが、よろめきながらわれわれの門にたどりつき、息絶える前にある情報を伝えたのです」
シルクの顔から血の気がひいていた。「だれのしわざだったんだ?」
「まだ調査中だ、ケルダー」いとこは答えた。「もちろん、何人か容疑者はいるが、判事の前に連れていけるほど確かなことはなにもつかめてない」
皇帝はけわしい表情で、すわっていた椅子から立ち上がった。「このことについて、知っておく必要のある者が何人かいる」かれはすごみのある声で言った。「一緒にきてくれるか、カルドン王子?」
「もちろんです、陛下」
「失礼する」ヴァラナは一同に言った。「一刻を争う問題なのだ」かれはドラスニア大使をしたがえて部屋から出ていった。
「ベスラはひどく苦しんだのか?」シルクは苦痛にみちた声で、通称ヴェルヴェットにきいた。
「暗殺者たちはナイフを使ったのよ、ケルダー」彼女はぽつりと答えた。「ナイフは決して気持ちのいいものじゃないわ」
「そうか」シルクのイタチみたいな顔がこわばった。「ベスラ殺害の理由について、彼女はなにか手がかりを残していったのか?」
「わたしの考えでは、いくつかのことと関係があると思うの。ベスラはかつてヴァラナ皇帝に、かれの息子の殺害計画を知らせたことがあると言ってたわ」
「ホネス一族だわ!」セ?ネドラが金切り声をあげた。
「どうしてそんなことを言うんだ?」シルクがすばやくたずねた。
-
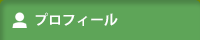
-
-

-

- 未分類 (73)
-

-

-

-



