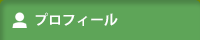「じゃあ、きまりだ」ガリオンは言った。「ぼくたちの計画をきみたちが部隊に伝えてくれるなら、ダーニク公開大學 課程とぼくはこれから空想上のかがり火のおこしかたを習いはじめる」
それから一時間ばかりたったころ、リヴァの部隊は緊張ぎみに行動を開始した。全員がいつでも武器をとれる体勢で、灰緑色のハリエニシダのしげみを歩いていった。前方に丘陵の
裾野が黒々と横たわり、一行のたどる草深い道は、熊神教の信者たちのひそむ石ころだらけの峡谷へまっすぐつづいていた。その峡谷に足をふみいれたとき、ガリオンははやる気持ち
をおさえ、意志の力を働かせて、ポルおばさんに教わったことをひとつのこらず慎重に思いおこした。
計画はびっくりするほどうまくいった。最初のグループ公開大學 課程が武器を高々とかざし、勝利の叫びを発しながら隠れ場所からとびだしてきたとき、ガリオン、ダーニク、ポルガラは間髪を
いれず残る三つの雨溝の入口を封鎖した。突撃してきた信者の面々は、突然仲間の戦闘参加をさまたげた炎の出現に驚愕した。かれらはひるみ、勝利の声は無念の呻きに変わった。ガ
リオン率いるリヴァの兵士たちは、一瞬のためらいをすかさず利用した。最初のグループはじわじわと撃退され、さきほどまで潜んでいた雨溝に閉じ込められた。
ガリオンは戦いの経過にはほとんど注意をはらうゆとりがなか公開大學 課程った。レルドリンとならんで馬にまたがっていたかれは、戦いがくりひろげられている雨溝の向かいにある、もうひと
つの雨溝の入口に、火のイメージと、熱さの感覚と、火の燃えさかる音を投影するのに全神経を集中していたのだ。おどる炎をすかして、信者たちが実際には存在しない強烈な熱気か
ら顔を守ろうとしているのがぼんやりと見えた。そのとき、だれひとり思いもしなかったことが起きた。ガリオンに封じ込められた信者たちが、あたふたとよどんだ池の水をバケツい
っぱい、空想の火にかけはじめたのだ。むろんジュッと音がするわけでもなく、幻影を消そうとするその試みは目に見えるいかなる効果ももたらさなかった。少ししてから、ひとりの
信者がへっぴり腰でおそるおそる火をくぐりぬけた。「これは偽物だ!」かれは肩ごしにうしろへ叫んだ。「この火は偽物だぞ!」
「だが、これは本物だ」レルドリンが不気味につぶやいて、その男の胸を矢で射抜いた。信者は両手をあげて、火のなかにあおむけにたおれた――男の死体は焼けなかった。それがい
っさいを暴露してしまったことは言うまでもない。最初は数人だったのがしだいにふえ、信者たちはなだれをうってガリオンの幻からとびだしてきた。レルドリンの両手が猛スピード
で動いて、雨溝の入口の信者たちに次々に矢を射ち込んだ。「数が多すぎるよ、ガリオン」レルドリンは叫んだ。「ひとりじゃくいとめられない。退却だ」
「ポルおばさん!」ガリオンはどなった。「やつらが火をくぐってでてきた!」
「押し戻すのよ」ポルガラが声をはりあげた。「意志の力を使うのよ」
ガリオンはさらに神経を集中させて、雨溝からあらわれる群衆に堅固な意志の壁をつきつけた。はじめのうちはうまくいくかに思えたが、並たいていの努力ではないので、すぐに疲
れてきた。あわてて立てた壁のはじがすりきれだして、ガリオンが死にものぐるいで撃退しようとした連中がその弱い部分に気づきはじめた。
ありったけの集中力で壁を維持しようとしているとき、遠雷に似た不機嫌なとどろきがかすかに聞こえてきた。
「ガリオン!」レルドリンが叫んだ。「騎馬戦士だ――何百といるぞ!」
ガリオンは暗澹たる思いですばやく峡谷を見あげた。騎馬戦士の一群あらわれて、けわしい横断路をおりてくる。「ポルおばさん!」ガリオンはさけぶなり、〈鉄
拳〉の大剣をぬこうと背中に手をのばした。
ところが、騎馬戦士の波はガリオンの目の前まで来るとくるりと向きを変え、ガリオンの壁をいまにも破ろうとしている最前列の信者たちにつっこんだ。この新たな兵力を構成して
いるのは、革のように丈夫でしなやかな黒ずくめの男たちだった。どの男の目も一様に奇妙に角ばっている。
「ナドラク人だ! まちがいない、ナドラク人だ!」バラクが峡谷の向こうから叫ぶのが聞こえた。
「ナドラク軍がこんなところでなにをしているんだ?」ガリオンはひとりごとのようにつぶやいた。
「ガリオン!」レルドリンが大声をあげた。「騎馬戦士のまんなかにいるあの人――ケルダー王子じゃないか?」
すさまじい乱闘の中へ突進する新たな軍団は、戦いの流れをみるまに変えた。かれらは雨溝の入口からでてくる信者たちの正面につっこみ、おどろいている信者たちにおそるべき痛
手を加えた。