一行がジャーヴィクショルムにいたる曲がりくねった入り江の広い口にはいったのは、日が沈もうというときだった。「すっかり暗くなってから接近したほうがいいんじゃないかな?」〈海鳥〉号の前部甲板でガリオンは他の王たちにたずねた。
アンヘグは肩をすくめた。「わしらが行くことは連中にはわかっているんだ。ハルバーグ海峡を出てからずっと見張っていたからな。おまけに、わしらがここにいることも知っているんだから、崖の上の連中は全力をあげて艦隊を見張ろうとするだろう。だから、そのときがきたら、きみとブレンディグは楽々背後から連中にしのびよることができるはずだ」
「そうか、なるほど」
バラクが片腕のブレンディグ将軍と一緒にやってきた。「綿密に計算したところでは、真夜中ごろに出発するのがよさそうだな」バラクは言った。「ガリオンと残りのおれたちがまず斜面をよじのぼって、都市の裏手にまわりこむ。ブレンディグとかれの部下たちがそのあと斜面をのぼって、投石器をうばいとる。空が白みだしたらすかさず、ブレンディグが北側に石を投げつけるんだ」
「そのすきにガリオンは所定の位置にたどりつけるのかね?」フルラク王がきいた。
「その時間はたっぷりありますよ、陛下」ブレンディグがうけあった。「バラク卿の話では、てっぺんまでのぼってしまえば、地形は平坦そのものだということですから」
「木もほうぼうに立ってる。隠れる場所は木がいくらでも提供してくれるよ」バラクは言った。
「都市を攻撃するときだが、距離はどれくらいあるんだろう?」ガリオンがたずねた。
「ええと、五百ヤードってところだな」バラクが答えた。
「かなりあるね」
「おれなら走っていきたいね」
入り江のおだやかな水面の上に夕暮れがゆっくりと訪れて、両側にそそりたつけわしい崖を紫色にそめた。ガリオンはわずか数時間後には部下たちとよじのぼる予定の急斜面を、消えようとする最後の日差しでくまなく点検した。頭上でなにかが動いたのに気づいて視線を上げると、白いぼんやりしたものが紫色の静かな空中を音もなくすべっていた。白くやわらかな羽が一枚、ゆっくりとまいおりてきて少しはなれた甲板の上に落ちた。ヘターがおごそかに歩みよってそれをひろった。
そのすぐあとに、青いマントに身をつつんだポルおばさんが甲板を歩いてきてかれらに合流した。「造船所に接近したら、じゅうぶん注意しなければだめよ」ブレンディグとそばに立っていたアンヘグにポルおばさんは言った。「敵は投石器を浜へおろして、こちらの接近をはばもうとしているわ」
「予測していたことさ」アンヘグはたいして気にしていないらしく肩をすくめた。
「彼女の言うことにはちゃんと耳をかたむけたほうがいいぜ、アンヘグ」バラクがおどかすように言った。「おれの船を沈めでもしたら、そのほおひげを一気にむしりとってやるからな」
「自分の国の王に話しかけるにしちゃ、ずいぶんと思いきった言い方だな」シルクがジャヴェリンにささやいた。
「都市の裏手の警備はどの程度なのかな?」ガリオンはポルガラにきいた。
「城壁は高いし、門は頑丈そうだけれど、兵の数は少ないわ」
「いいぞ」
ヘターが無言でポルガラに羽をわたした。
「あら、ありがとう。うっかり見落とすところだったわ」
なだらかにうねる台地につづく丘の斜面は、ガリオンが〈海鳥〉号の甲板からながめて判断していた以上にけわしかった。真夜中の暗闇のなかではほとんど見えない砕けた岩のかたまりが、足の下で意地悪くすべり、斜面に密生する背の低いしげみの枝は、必死で上へのぼろうとするガリオンの顔や胸をわざとつついてくるように思えた。鎖かたびらが重くて、かれはたちまち汗みずくになった。
「骨がおれるな」ヘターがひとこと言った。
ようやくそのけわしい斜面をのぼりきったときには、淡い銀色の月がのぼっていた。のぼりついてみると、そこに広がる台地はモミとトウヒの鬱蒼たる森におおわれていた。
「これは思っていたより時間をくいそうだな」バラクがおいしげった下生えを見ながらつぶやいた。
ガリオンはひとやすみして息をついた。「小休止しよう」友人たちに告げた。行く手にたちふさがる森をガリオンはむっつりとにらみつけた。「ぼくたち全員が森をつっきろうとすれば、崖の上の投石器のやつらに気づかれてしまうだろう。ここは斥候を送りだして小道かなにかをさがしたほうがいいと思う」
「おれにちょっと時間をくれ」シルクが言った。
「だれか連れていったほうがいいよ」
「足手まといになるだけだ。すぐに戻る」小男は森の中に見えなくなった。
「ちっともかわらないね、かれは」ヘターがつぶやいた。
バラクが短く笑った。「本気でシルクが変わると思ってたのか?」
「夜明けまであとどのくらいだと思われる、閣下?」なチェレク人にたずねた。
「二時間――三時間ぐらいかな」バラクは答えた。「斜面に相当手間取ったからな」
弓を背中にしょったレルドリンが暗い森のはじにいたかれらのところへやってきた。「ブレンディグ将軍がのぼりだしましたよ」
「片腕だけでどうやってあそこをよじのぼるんだろう」バラクが言った。
「ブレンディグのことならそう心配することはない」ヘターが答えた。「やりだしたことはいつでもちゃんとやりとげる」
「たいした男だな」バラクは感嘆のおももちだった。
-
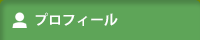
-
-

-

- 未分類 (14)
-

-

-

-



