馬車は這うようにのろのろと進んだ。高い、薄い雲がふたたび太陽の姿をかくし、重苦しい寒さが南アルガリアのどこまでも平たい大地を覆っていた。馬車に乗り込んだガリオンは疲労で重くぼんやりした頭を抱えながらも、意識のないベルガラスにかがみ込むポルおばさんを食い入るように見つめていた。眠ることなど問題外だった。いつ何どき、あらたな脅威がふりかかるか知れず、そうなったらただちにおばさんを助けて、かれの〈意志〉と護符の力を集めて加勢にくわわるつもりだった保濕精華。小さな顔に悲しげな表情を浮かべたエランドはおとなしく椅子に座り、両手でダーニクが作ってやった小袋をぎゅっと握りしめていた。ガリオンの耳のなかで〈珠〉はなおも歌い続けていたが、いつしかその響きはたえまない穏やかなものになっていた。ラク?クトルを離れてから何週間もたつうちにかれはすっかりその存在に慣れてしまった。ときおり周囲が静かなときや疲れているときなど、歌はあらたな力をもってよみがえるのだった。それはどこか心慰められる調べだった。
ポルおばさんはかがみ込むとベルガラスの胸にふれた。
「どうかしたの?」ガリオンは鋭くささやいた。
「何でもないわ、ガリオン」彼女は落着きはらって言った香港摩星嶺。「お願いだからわたしが動くたびにいちいち聞くのはやめてくれない。もし何かあったら、あなたに言うわ」
「ごめんよ――ただ心配だっただけなんだ」
彼女はふり向いて、きっとガリオンを見すえた。「あなたは何でエランドを連れてシルクやダーニクと一緒に上にいないの」
「だってぼくが必要になったらどうする?」
「そのときはあなたを呼ぶわ」
「でも本当にぼくがいた方がいいんじゃないか」
「いいえ、むしろいてくれない方がありがたいわ。必要なときには呼びますからね」
「だけど――」
「今すぐ行くのよ、ガリオン」
かれにはこんなとき何を言ってもむだなことはわかっていた。ガリオンはエランドを箱馬車の戸口まで連れていき、上にあがった。
「容体はどうだい」シルクがたずねた。
「何でぼくにわかる? わかることといえば、自分が追っぱらわれたことくらいさ」ガリオンはいささかぶっきらぼうな口調で答えた。
「それはいい兆候じゃないか」
「たぶんね」ガリオンはあたりを見まわした。西側にそって長い丘が続いていた。それらを見おろすようにして巨大な石積みの塔がそびえたっていた。
「あれが〈アルガーの砦〉だ」ダーニクが指さしながらガリオンに言った。
「あんなに近いのかい」
「いや、まだまる一日はかかるな」
「どれくらいの高さがあるんだい」
「少なくとも四、五百フィートはあるね」シルクが言った。「なにしろアルガー人が数千年もかかって築きあげてきたものだからな。家畜の出産期が終わったあとのいい気晴らしさ」
バラクがあがってきた。「ベルガラスの具合はどうだ」大男は近づきながら言った。
「少しはよくなってきたんじゃないかと思う」ガリオンは答えた。「でも本当のところはぼくにもわからないんだよ」
「まあ明るい材料ではあるな」大男は行く手の溝を指さしながら言った。「あそこは迂回した方がよさそうだ」かれはダーニクに言った。「チョ?ハグ王の話ではこのあたりの道はあまりよくないとのことだったからな」
ダーニクはうなずいて、馬車の方向を変えた。
その日いちにちというもの、アルガー人の〈砦〉は西の地平線を背に、焦げ茶色の丘陵地帯にそびえ、立ちはだかるように見えた。
「あれは人目をそらすための建造物なのさ」シルクはだらしなく馬車に背をもたせかけながら言った。
「それはどういう意味ですか」ダーニクがたずねた。
「アルガー人は遊牧民だ」小男が説明した。「かれらはこんな形の箱馬車に住んで家畜を追って暮らしている。〈砦〉はマーゴ人にとっては格好の攻撃目標だ。あれはそのために建てられたのさ。まったくもって実用的だと思わんかね。そうすれば何もいちいちこの広い平原全部を見張っていなくともすむんだ。マーゴ人はいつも〈砦〉を攻撃してくるし、やつらを一掃するには実におあつらえむきの場所だ」
「だがいつかマーゴ人だって気づくんじゃありませんか」ダーニクは疑わしげに言った。
「むろん、そうだ。だがそれでも連中は〈砦〉に引き寄せられてあそこへ行かずにはいられないのさ。中がもぬけの殻だとはどうしても信じられないらしい」シルクはちらりとイタチのような笑みを見せた。「マーゴ人たちがいかに頑固かきみだってよく知ってるだろう。まあ、とにかくそうしているうち、アルガーの各氏族で一種の競争のようなものが行なわれるようになった。毎年かれらは石を積む高さを競いあい、かくして〈砦〉はますます高くなりつつあるというわけだ」
「カル=トラクは本当に八年間にもわたって包囲したのかい」ガリオンがたずねた。
シルクはうなずいた。「トラク軍が〈砦〉に押し寄せて、アンガラクの海の大波が打ち寄せて砕け散る光景を思わせたそうだ。まあ、そのまま包囲していてもよかったんだが、食糧が底を尽いてしまったんだ。大きな軍隊じゃいつも問題になることだな。軍を起こすのは簡単だが、めしの時間になるとたちまち大混乱におちいるのさ」
かれらが人工の山に近づくと同時に、門が開き、出迎えの一団があらわれた。白い乗用馬に乗りヘターを従えて先頭にたっているのはシラー王妃だった。かれらはある地点まで来ると立ち止まり、そのまま馬車が近づくのを待った。
ガリオンは箱馬車の小さな戸をはね上げた。「着いたよ、ポルおばさん」かれは小声で知らせたYumei水光精華。
「そう」彼女は答えた。
-
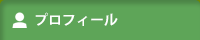
-
-

-

- 未分類 (18)
-

-

-

-



