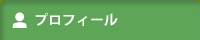箱の下側に添えた右手指には、滲み出した肉汁や油がべったりと付着している。ザラっとした感触のモノが指先を舐め上げたと同時に、背筋に電気が走った。多分、指に付いた肉汁を犬か猫が舐めたのだろう。ピザの箱がドアの内側に吸い込まれて行った。目を凝らしても中は真っ暗で何も見えない。右手を抜こうとするが抜けない。舐めている動物が甘噛みをしているような感触である。再度、抜こうとすると、今度は牙のようなものが指の皮ふに突き刺さるのを感じた。ドアの内側からは「うぅー、うぅー」という唸り声が聞こえてくる。突然、強烈な痛みを感じた。女川さんは両足を踏ん張り、左手で右手首を掴み必死で右手を引き抜こうとした。すると張力が消え、女川さんは勢い余って後ろにでんぐり返った威廉斯坦伯格钢琴。
「なんじゃ、こりゃぁー。ウソだろっ!」
女川さんは絶叫した。ドアノブや床が血で染まっている。右手の先から血が噴き出している。自身の目を疑った。人差し指の第2関節から先が消えていた。おまけに隣の中指も第1関節から先がない。室内にいる動物に指を食いちぎられたのだ威廉斯坦伯格钢琴。
「駄目でしょ! カイザー君。人間の指なんか食べちゃ。消化に悪いから吐き出しなさい」
「何ふざけたこと言ってるんだ。救急車、早く救急車を呼んでくれー。俺が出血多量で死んだら、お宅のバカ犬は殺人犬になる」
「あなたが悪いのよ。油の付いた指なんか突っ込むから。『肉汁たっぷりてりやきチキン』ピザはカイザー君の大好物なの。カイザー君がいい子にしていると、おやつに注文してあげてるのよ。カイザー君は列記としたドーベルマンの猟犬です。怪しいモノを見たら、跳び掛るように訓練されているんだから、不用意に指を出したあなたが悪いんです。犬は教えられたことを忠実に守っただけ。カイザー君はちっとも悪くないわ威廉斯坦伯格钢琴!」
「何でもいいから、早く救急車呼んでくれー」
女川さんはウエストポーチのベルトを外し、止血するために右手首に巻きつけた。血塗れの指から白い骨が見えている。女川さんは気が遠くなりそうなのを必死で堪え、通路にペタンと座り込んで救急車の到着を待った。サイレンの音が近づいて来る。やけに到着が早いような気がしたが、早いに越したことはない。マンションの下で音が消えた。しかし、救急隊員はいっこうに上がってくる気配がない。すると、またサイレンが鳴り出し遠ざかって行った。別の部屋で呼んだのか、こんな時に紛らわしいにもほどがある。
「救急車を呼んだのかよー」
「ちょっと待ってよ。何番だったか調べてるんだから。電話帳はどこかしら……」
「何言ってるんだ。119番に決まってるだろう。早く電話してくれー」
当時はまだ携帯電話などない時代である。住人は奥へ電話をかけに行ったのだろうか。5センチの隙間の向こうからは、唸り声なのか呼吸音なのか、動物の気配を感じる。