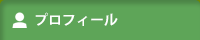ロバート・ブレイクの死を、落雷のため、あるいは放電によっ口服 避孕 藥て神経に強い衝撃をうけたためだとする世人の所信に対して、用心深い調査家は、疑義をさしはさむのをためらうだろう。確かに
ブレイクのまえにあった窓のガラスが割れていなかったのは事実だが、自然は数多くの珍奇な離れ技をやってみせるものだ。ブレイクの死顔にしても、ブレイクが目にしたものとは何の関係もな
い、原因不明の筋肉のひきつりによるものかもしれないだろうし、日記の内容にしたところで、ブレイクが自ら掘りおこした古伝や地方の迷信にでも刺激され、奔放な想像力を働かせた、その所
産なのだともいえるだろう。フェデラル・ヒルの荒《さ》びれた教会における異様な状態については――如才ない分析家なら、ためらうことなく、知ってか知らずしてかは別として、ブレイクが
少なくともいくぶんは内密の関係をもっていた、何らかの狂言であるという見方をとる。
というのも、つまりは被害者が、神話、夢、恐怖、迷信の分野に一身をささげつくし、奇怪か均衡飲食つ幽鬼めく場面や効果の追求にいれこんでいた、作家であり画家であったからなのだ。ブレイクは
かつて――自分と同様に隠秘学や禁断の伝承に深く没頭する風変わりな老人を訪ねるため――町にあらわれたことがあるが、町での滞在は死と炎の只中のうちにおわった。ブレイクをミルウォー
キーの自宅から離れさせたのは、およそぞっとしない勘のようなものが働いたためにちがいない。日記には逆のことが記されているとはいえ、ブレイクは古譚をいろいろ知っていたのかもしれな
いし、そしてブレイクの死は、文学的には非難されるべき運命にあった鬼面人を威《おど》す悪戯を、蕾《つぼみ》のうちに摘《つ》みとったのかもしれない。
しかし証拠のすべてを調べ、相関関係をわりだした人びとのなかには、合理的とも平凡ともいえない臆測に執着する者が何人か残っている。そういう者たちは、えてしてブレイクの日記のほと
んどすべての記述を額面どおりにうけとり、たとえば、古い教会の記録の紛れもない信憑性、忌み嫌われ抗衰老護膚品る邪教の〈星の知慧《ちえ》派〉が一八七七年以前に遡《さかのぼ》って存在する、証明
済みの事実、一八九三年にエドウィン・M・リリブリッジという好奇心の強い記者が失踪したことの記録、そして――とりわけ――若い作家の死顔にうかんでいた悍《おぞ》ましいまでにゆがん
だ恐怖の表情といった事実を、意味深長に指摘。ブレイクの日記には、古い教会の塔のなかにあったと記されているが、そこではなく、窓のない黒ぐろとした尖《とが》り屋根で
発見された、奇怪な装飾のある金属製の箱と妙に角ばった石とを、極端な盲信に駆りたてられるまま湾に投げすてたのは、そういう者たちのひとりだった。その男――奇妙な伝承に興味をもつ評
判のいい医者――は、公私にわたってはなはだしく非難されたが、ほうっておけばあまりにも危険すぎるものを地上からとりのぞいたのだと、自信たっぷりに主張したものだ。
こうした二派にわかれる考え方のなかで、読者は自ら判断を下さなければならない。資料は懐疑的な角度から実質のある委細を与えてくれるし、加えて、ロバート・ブレイクが見た――あるい
は見たと思いこんだ――か、見たふりを装った情景も、素描というかたちで残されている。さて、日記を仔細に、私心なく、ゆっくりと調べることによって、一連の謎めいた出来事を、その中心
人物が述べている観点から要約してみよう。
若きブレイクは、一九三四年から三五年にかけての冬に、プロヴィデンスにもどり、カレッジ・ストリートはずれの草地に建つ古びた住居の上階をかりきった――そこはブラウン大学のキャン
パスに近い、東にのびる大きな丘の頂で、背後には大理石造りの大学付属ジョン・ヘイ書館が位置している。人なつっこい大きな猫が何匹も、手近な納屋の屋根で日なたぼっこをしているような
、牧歌的な古色をたたえた小さな憩の庭にある、こぢんまりと