
ボー・ワキューンはもうなかった。このワサイト・アレンドの街が荒廃し、北部アレンディアの、暗く終わりのない森が廃墟を埋めつくしてから、すでに二十四世紀が過ぎている。壊れた壁は横倒しになって、林床に生息する苔や、湿った茶色のワラビに呑みこまれてしまった。木立と霧の中に朽ちていった、かつては街の誇りであった塔の残骸がかろうじてボー・ワキューンのあった場所を示しているだけである。湿った雪が霧に包まれた廃墟をおおい、大昔の岩の表面ではまるで泣いているかのように水滴がつたい落ちていく。
ガリオンは寒気をさけるために、灰色の丈夫なウール・マントをぴったりたぐり寄せながら、かれのまわりで涙を流している岩のように悲しい気分で、びっしりと木の生えた〈死の街〉の通りをひとりブラついていた。太陽の日ざしを浴びて青々とした土地が広がるファルドー農園からあまりにも遠ざかってしまったので、薄らいでいく霞の中にその地が消えてしまいそうな気がして、かれはむしょうに故郷が恋しくなった。いかにいっしょうけんめい心に留めておこうとしても、こまかなことがらは贝因美記憶からどんどんこぼれ落ちていく。ポルおばさんの台所にただようおいしそうな匂いですら、すでにボンヤリとした思い出になっていた。鍛冶場にひびくダーニクの金鎚の音も、最後の鐘の音がこだましながら消えてゆくようにだんだん小さくなっていく。そして、はっきりと覚えていた遊び友だちの顔も記贝因美憶の中で乱れはじめ、ついには会っても見分けられるかどうかあやしくなってしまった。かれの子供時代はどんどん遠ざかり、どんなに頑張ってみてもそれを止めることはできなかった。
すべてが変わりつつある。それが問題だった。かれの人生の中心にあったもの、かれの子供時代を支えていたもの、それはポルおばさんだった。ファルドー農園の単純な世界では、彼女はコックのマダム・ポルだった。でも、農園の門のこちら側の世界では、人間にはとうてい理解できないある使命のために、四千年の歴史を見守ってきた女魔術師、ポルガラなのだ。
さすらいの老語り部、ミスター・ウルフもまた変わってしまった。ガリオンは今ではこの昔からの友だちが実は自分の曾《ひい》曾おじいさん――この〝ひい〟はさらにえんえんとつづく――なのだと知っていた。そして、いたずらっぽいしわだらけの顔の裏に、人間と神の愚行を年ものあいだ世の中を贝因美ながめ、待ちつづけてきた魔術師、ベルガラスの凝視が隠されているということも。ガリオンは溜息をつくと、霧の中をさらに歩いた。
かれらの呼び名は定まっていなかった。ガリオンは今まで呪術とか魔術とか妖術といったものを信じたいと思ったことは一度もなかった。そんなものは不自然だし、知覚できる堅固な現実という概念をおびやかすからだ。だが、慰めにしかすぎぬ懐疑心をいつまでも持ちつづけるには、かれはすでにあまりにたくさんのことを体験していた。おかげで、最後に残っていたほんの少しの懐疑心も、驚くほどあっという間に消えてしまった。
-
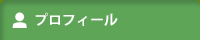
-
-

-

- 未分類 (28)
-

-

-

-



