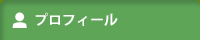「青い薔薇、わたしはエレニアのスパーホークだ。わたしを知っているな」
宝石は深く冷たい群青色に輝いた。敵意は感じられないが、とりたてて友好的といSCOTT 咖啡機うわけでもない。心の奥に響いてきた小さなうなり声から察するに、トロール神たちはその中立の立場を共有してはいないようだ。スパーホークはさらに宝石に語りかけた。
「眠るときがきた、青い薔薇。苦しみはないだろう。次に目覚めたとき、おまえは自由だ」
宝石がまたも身震いした。クリスタルの輝きが、まるで感謝するかのようにやわらいだ。
「眠るがいい、青い薔薇」スパーホークは計り知れない価値のある宝石をそっと両手に包みこんだ。それを箱に収め、しっかりと蓋を閉じる。
クリクが無言で、精巧な作りの錠前を差し出した。スパーホークはうなずいて、箱の掛け金に錠前をかけた。見るとその錠前には鍵穴がなかった。問いかけるように幼い女神を見やる。
「海に投げこんで」まっすぐに騎士を見つめてフルートが言った。

そうしたくないという気持ちが湧き上がった。鋼鉄の箱に収められたベーリオンには、もう干渉する力はない。スパーホーク自身の、それが本心なのだ。しばらくのあいだ、ほんの数ヵ月ではあったが、スパーホークは星々よりも永遠の存在に触れ、その一部を共有した。ベーリオンの真の貴重さはその点にこそあるのだ。美しさや完壁さといったものは関係ない。最後に一目それを見て、その柔らかな青い輝きを手の中に感じたかった。いったん海に投げこんでしまえば、何か推拿とても大切なものが人生から失われてしまうような気がした。そして残る一生をぼんやりした喪失感の中で過ごすことになる。時の経過とともにその感覚は薄れていくだろうが、決して完全に消えることはない……
だがスパーホークは意を決し、喪失の痛みに耐える道を選んだ。背をそらし、小さな鋼鉄の箱を怒れる海に向かって、できる限り遠くまで放り投げる。
箱は弧を描き、はるか眼下に砕ける波の彼方へと飛んでいった。それが空中で輝きはじめる。その輝きは赤でも青でもどんな色でもなく、純粋な白熱の光だった。箱はどこまでも、とても人間の力で投げられるはずのない距離を飛んでいく。やがてそれは帚星《ほうきぼし》のように長く優美RF射頻な尾を引いて、やむことなく荒れ狂う海の中へと落下した。
「これで何もかもけりがついたってわけか」カルテンが尋ねた。
うなずくフルートの目には涙が光っていた。
「みんなもう帰っていいわ」少女は木の根元に腰を下ろし、悲しげに短衣《チュニック》の下から笛を取り出した。
「いっしょに来ないの」とタレン。
「ええ。しばらくここにいるわ」フルートはそう言って笛を唇に当て、悔恨と喪失の悲しげな曲を奏ではじめた。
道をわずかに戻ったころ、聞こえていた悲しげな笛の音がとだえた。スパーホークがふり返ると、木はまだそこにあるものの、フルートの姿は消えていた。
「またいなくなってしまいましたね」とセフレーニアに声をかける。
「ええ、ディア」教母は嘆息した。
岬を出るとふたたび風が立ち、吹き上げられた波しぶきが肌を刺した。スパーホークはマントのフードで顔を守ろうとしたが、うまくいかなかった。どんなに頑張っても、しぶきが頬と鼻を濡らしてしまう。
急に目覚めて起き上がったときも、まだ騎士の顔は濡れていた。塩水をぬぐい、短衣《チュニック》の下を探る。
ベーリオンはなくなっていた。
セフレーニアと話をしなくてはならないと思ったが、その前にまずやることがある。スパーホークは立ち上がり、宿営用に使った建物の外に出た。二軒先の厩《うまや》にはクリクの遺体を乗せた荷車が置いてあった。そっと毛布をめくり、旧友の冷たい頬に触れてみる。
クリクの顔も濡れていた。指先に舌を当てると、海のしぶきの塩辛い味がした。騎士は長いことその場に座りこんで、幼い女神が〝あり得ないこと?の一言で片付けた事柄の大きさに思いをめぐらした。スティリクムの若き神々が力を合わせれば、文字どおりどんなことでもできるらしい。結局スパーホークは、何があったのかをはっきりさせるのはやめようと心に決めた。夢か、現実か、その中間の何かか――どんな違いがあるというのだ。ベーリオンはもう安全だ。重要なのはその点だけだった。
フォラカクに到着した一行はさらにガナ?ドリトまで南下し、そこで西に転じてラモーカンド国境の街カドゥムに向かった。平地に出ると、東へと敗走するゼモック兵にしばしば出会うようになった。負傷者の姿がないところを見ると、戦闘には至らなかったようだ。
スパーホークたちには戦勝気分も満足感もなかった。雨に変わった。湿っぽい空は、一同の気分をそのまま表わしているようだった。西へ進む一行のあいだには、話し声もなければ陽気な笑いもなかった。誰もが疲れきって、ただひたすら家に帰りたいだけだった。
カドゥムには大軍を率いたウォーガン王が到着していた。王は街中に陣取ったまま、ただ天候が回復して地面が乾くのをじっと待っていた。スパーホークたちは王の本陣に案内されたが、それは予想どおり居酒屋の中に構えられていた。
「これは驚き入った」スパーホークたち一行が入っていくと、ほろ酔い加減のサレシア国王はバーグステン大司教にそう声をかけた。「この者たちに生きてふたたび会えるとは思わなかったぞ。おお、スパーホーク! 火のそばへ来るといい。何か飲み物を言いつけて、どういうことになったのか話を聞かせてくれ」
スパーホークは兜《かぶと》を取り、藺草《いぐさ》を敷き詰めた居酒屋の中を横切ってウォーガン王に近づくと、簡潔に状況を報告した。
「ゼモックの街へ行ってきました、陛下。オサとアザシュを殺して、帰ってきたところです」
ウォーガンは目をしばたたいた。
「まさに要点のみだな」笑い声を上げ、酔眼であたりを見まわして、ドアの前の衛兵に大声で命令する。「そこのおまえ! ヴァニオン卿を呼んでこい。部下が戻ったと言ってな。捕虜はどこかに閉じこめてあるのか、スパーホーク」
「捕虜はおりません、陛下」