おじけづく馬をひいて、かれらは一列になってシルクのあとから傾いた石段をおりていった。どこか下のほうからごぼごぼと水の流れる音がする。石段の下についたとき、ガリオンは狭い通路が広がって大きなほら穴のような部屋になっているのに気づいた。巨大な石のアーチが屋根のようにせりだし、いぶるたいまつによってぼんやり照らされている。部屋のまん中は黒い油のようにとろりとした水に満たされ、細い通路がその水たまりの三面を走っていた。通路につながれているのはかなり大きな黒塗りのはしけで、黒装束の漕ぎ手が両側に六人ずつすわっている。
そのはしけの横の通路に、ヴェルヴェットが立っていた。「一度にふたりしか渡れないんです」彼女は一行に言った。丸天井の室内で声がうつろにひびいた。「馬も乗せなきゃなりませんから」
「渡るですって?」セ?ネドラが言った。「どこへ渡るの?」
「ネドレインの南岸へですわ」とヴェルヴェット。
「でも、わたしたちはまだ城壁の内側にいるのよ」
「じっさいには、城壁の下にいるんです、セ?ネドラ。わたしたちと川をへだてているのは、城壁の外側の表面を形成している大理石の板二枚だけなんです」
そのとき薄暗がりのどこかで重い巻き上げ機のきしむ音がして、地下の港の正面の壁がゆっくりと開き、たっぷり油をさした大きな鉄の蝶番が回転して壁が左右にわかれはじめた。二枚の石板がのろのろと開いたとき、その向こうにガリオンは雨のえくぼのついた川の水面を認めた。向こう岸が濃い霧にかすんでいるのも見える。
「じつに巧みだ」ベルガラスがうなった。「この家はいつごろからここにあるんだね?」
「何世紀も前からです」ヴェルヴェットが答えた。「だれもが抱く願望を満たすために建てられたんですわ。折りにふれて顧客のひとりは人に見られずに都市を出たがったり――都市にはいりたがったりします。ここはそのためにあるんです」
「どうやってこのことをつきとめたんだい?」ガリオンはたずねた。
リセルは肩をすくめた。「ベスラがこの家の所有者だったんです。彼女がジャヴェリンにこの秘密を教えたんですわ」
シルクはためいきをついた。「彼女は墓にはいってもおれたちに援助の手をさしのべているんだ」
一行はふたりずつはしけに乗り、霧深い雨のふるネドレイン川を渡って、背後に柳が密集する霧につつまれた細い砂の岸におりたった。最後にヴェルヴェットが渡ってきたときには真夜中を三時間はすぎていただろう。「漕ぎ手たちが砂についたわたしたちの足跡を消してくれます」彼女は言った。「それも料金のうちなんです」
「ずいぶん高くついただろう?」シルクがきいた。
「そりゃもうすごいわよ。でもドラスニア大使館の予算から出てるんですもの。あなたのいとこはそれがあんまり気にいらなかったんだけれど、わたしが説きふせたの――最終的には」
シルクは意地悪そうににんまりした。
「夜明けまであと数時間です」ヴェルヴェットはつづけた。「この柳の木立の向こう側に馬車道があって、一マイルほど川下で帝国街道に合流しています。都市の耳に届かないところにつくまでは、徒歩で進むほうがいいでしょう。馬が疾走するのを聞きつけたら、南門の軍団兵が不審に思うかもしれません」
かれらは霧雨のまとわりつく闇のなかで馬にまたがり、柳木立をぬけてぬかるんだ馬車道に向かった。ガリオンは速度をゆるめてシルクと並んだ。「あの家でなにがおこなわれていたんだい?」好奇心からたずねた。
「きみに想像できるかぎりのことがさ」シルクは笑った。「そして想像もつかない多くのことがね。金があり余っている人間にとっちゃ、あそこはありとあらゆるたぐいの気晴らしを提供してくれる願ってもない場所なんだ」
「知ってる顔がいた?」
「じっさい何人かいたよ――帝国で深い尊敬を得ている貴族の面々が」
すぐうしろで手綱をにぎっていたセ?ネドラがけがらわしげにフンと鼻を鳴らした。「男の人がああいうところに出入りする理由が理解できないわ」
「顧客は男だけじゃないよ、セ?ネドラ」シルクが言った。
「じょうだんでしょう」
「かなりの数の高貴な生まれのトル?ホネスのご婦人方が、あらゆる種類の方法で退屈をまぎらしている。むろん、仮面をつけているが――あとは堂々たるものさ。おれはある伯爵夫人に気づいたよ――ホービテ一族の中心人物のひとりだ」
「仮面をつけていたなら、どうしてわかったの?」
「彼女には目だつあざがあるんだ――めったに人目にさらさない場所にね。何年か前、彼女とじっこんの仲だったときにそれを見せてもらったんだよ」
長い沈黙があった。「これ以上この話はしたくないわ」セ?ネドラは、馬を小突いてかれらのわきを通り過ぎ前方にいるポルガラとヴェルヴェットのそばへ行ってしまった。
「たずねたのは彼女だぜ」シルクは無邪気にガリオンに抗議した。「きみだって聞いてただろう?」
数日間南へ進むうちに、天気は回復した。いつのまにかエラスタイドは過ぎてしまい、ガリオンはそのことを妙に残念に思った。ほんの子供だったときから、真冬の祝日は一年のハイライトのひとつだった。それをなおざりに見送ってしまうことは、きわめて神聖ななにかにそむいているような気がした。セ?ネドラのためになにか特別なものを買ってやれる時間があったらと残念でならなかったが、贈物がわりにできそうなのは、やさしいキスぐらいなものだった。
トル?ボルーンの数リーグ北へきたとき、十二人あまりのお仕着せ姿の召使いをひきつれて帝都へ向かう贅沢な身なりの男女に出会った。「おい。そこの」ビロードの服をきた貴族は、たまたま先頭にいたシルクにいばった口調でよびかけた。
「トル?ホネスはどんなようすだ?」
「例によって例のごとしですよ、閣下」シルクはへつらうように答えた。「暗殺、企み、陰謀――高貴な方々のいつものお楽しみだ」
「そういう言い方はあまり気にいらんな、おい」貴族は言った。
「わたしも、〝おい?と呼ばれるのはあまり気にいりませんね」
「びっくりするような話を聞いたのよ」毛皮で縁どりした赤いビロードのケープをつけたけばけばしい感じの婦人がせきこんで言った。「何者かがホネス一族を皆殺しにしようとしているって本当なの? 一族全員がベッドで殺されたそうだけど」
-
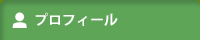
-
-

-

- 未分類 (28)
-

-

-

-



