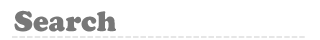囲いの中に捕えられた野生の馬(”MUSTANG”)が、人間を乗せるように、というよりはまさに字義のごとく男たちを乗せるよう調教されていくグロテスクの(競りのお披露目すらある)、しかしそれは『エコール』のように寓話めいたファンタジーであるどころか、それを習わしとして形作られる世界で5人の少女が一人ずつ屠られていく日々を誰が生き延びることができるのかという監禁ホラーですらあったといってもいい。オープニングから息苦しいほどに活写される、奔馬として生まれた者たちが世界に求める分け前が正当であればあるほど、それを奪われ続けることで緩慢に死んでいく彼女たちへの仕打ちはもはや殺人に近く、終盤の異様に張り詰めたサスペンスを生んでいるのは冤罪で死刑を宣告された少女たちによる脱獄の物語にほかならず、そこにあるのは『ヴァージン・スーサイズ』が告げたような実存の危機どころか既に生命の危機ですらあったことで、こちらまでが首を絞められるような強迫に苛まれることになる。とはいえこれが、差別や隷属のイズムは表出のパターンに過ぎないといってもいい悲劇的に入り組んだ問題であるのは、祖母(ニハール・G・コルダシュ)のように悪意のない善人や叔父エロル(アイベルク・ペキジャン)のような悪意を悪意と知ることのない罪人、要するに世界には中心があると考えてそこに躊躇なく依存する者と、それぞれを無数の中心にして繋がることで世界は在ると考える者の断絶によっているからで、最終的には同性への連帯よりも世界にかしずいてしまう祖母のような女性や、長髪=ゲイ扱いされる社会で髪をなびかせトラックを運転するヤシンや、密かに事情を汲んでくれる産婦人科の医師のように少女たちを援護する男性の配置にそれは端的に象徴されている。しかし最後にラーレ(ギュネシ・シェンソイ)がその胸に飛び込んだのがそうした垂直と水平の交錯について先鋭であろうディレク先生であったことによりこの一瞬のハッピーエンドが一気に現実の解を求めはじめることで、笑顔もガッツポーツも宙に浮いたままこわばってしまうのを止められないように思うのだ。その割り切れなさは、この断絶が人種も宗教も超えてイギリスやアメリカのシビルウォーの根底にあるものと共通するようにも思えるからで、したがってこの映画を評する補助線としてMMFRを用いるのは、その昂ぶりは理解するものの監督や作品に向かう歩みを止めてしまうようにも思えてしまい、少しばかりわだかまりを感じてしまうのが正直なところである。ルーレや彼女の戦友に肩を貸すように包み込むウォーレン・エリスとニック・ケイヴによるスコアは常に凛として優しいのだけれど、いつしかそれがレクイエムのように聴こえてきてしまうのがこの映画の抱えるハードな状況のどうにも避けがたい反映なのだろう。『コップ・カー』の疾走から百万光年離れた衝突に少しだけ泣きそうになった。
-


-
vistlip/SHIVA/ザアザア/Smileberry/バンギャ/V系むっちゃすき。けっこういろんなバンドさんの音楽聴いたりライブ行きます。人生悔いなく生きたい。ハンドメイド、買うのも作るのもすき。かなりの人見知り、口下手。社会人テニスやってまふ。
-
-

-

- 未分類 (46)
-

-
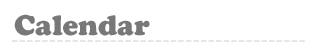
-

-