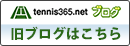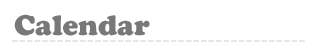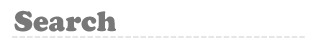火曜日 
沖縄戦70年「沖縄全戦没者追悼式」が行われた。3月に沖縄の大会に出た折、観光で「ひめゆりの塔」に行きましたが資料館で目にしたものは胸を締め付けられるものばかり、70年経過したとは思えない、つい最近のできごとのように迫ってくるものがありました。70年前にタイムスリップして彼女たちの悲鳴が資料館に渦巻いているかにおもえましたが、生き残っている数名の語り部は嫗となりその姿をみていると、何ともいえない気持ちになっていました。
ぼくは、終戦の翌年69年前に小学校に入学したことになる。昔の校舎は木造でおもむきがあった、校門の脇には確かに桜の木はあった。「そのお互いは母の手に引かれて校門をくぐりました。・・・・・・・・・」と恩師は同級会の案内の中にあったが、ぼくはまったく記憶がない。ぼくがどんな格好であったかだいたい察しはつく、その時の母の気持ちはどんなだっただろうかと、おもうとつらくなる。
1年生の時、女の先生からご褒美をあげると、期待していたらいきなりビンタをはられたのは長く心に刻まれていたできごと。2年生から戦地までは行っていないが訓練でしごかれたであろう19歳の恩師が赴任してきた。こびんちゃかで一見かわいい顔をしていたが、何かあれば容赦なくビンタがとんできた。女の子は尻をつねられていた。
教育熱心な親御は教室にたびたび姿を現して、そんな生徒は成績もよくかわいがられていた。思い出も半世紀以上過ぎれば風化して記憶は遠のいてゆくが、消え去らないものもある、これも一人の一つの人生に他ならない。
恩師は受付近くのソファーに益々小さくなって緊張したおもむきで坐っており、出席者から挨拶を受けてたが、耳も遠くこれが最後に思えた。3時間は瞬く間に過ぎ去っていった。話しをしたくて会話しょうとすれれば、何から話していいか分からなくなり、もどかしそうな二人になる。
一人、目の不自由な仲間がいた。小学校の頃はまだ大丈夫だった。いつからそうなったかは知らぬが、彼の挨拶で母親からあん摩になるように薦められたがあん摩にはどうしてもなりたくなかったという。人の体をもんで一生を過ごしたくないというのが事由だった。そして彼が一番立派に生きているように思えた。苗を育てて一円のホームセンターなどにおさめる仕事に成功しているようだった。
目が見えなくなって不自由なことはたくさんあったが、一つだけ良いことがあるという。もうみんな老いくたびれているでしょうがその姿は見たくない、ぼくの脳裏には皆の若かりし姿がそのまま残っていますと言うのだ。
感銘する言葉だった。正治くんの記憶の中のぼくはどんな顔をしているのだろう。