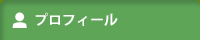「ドロスタ王は信用できるんだろうね」ガリオンはベルガラスの後に続いて、ゴミの散乱する居酒屋の裏小路を歩きながらシルクにたずねた。
「どの程度、衝撃を与えられたかによるな」シルクは答えた。「だがSCOTT 咖啡機開箱ある一点に関しちゃ、本当のことを言ってたぞ。まさに今のやっこさんはにっちもさっちも行かないところまで追いつめられているのさ。少なくとも、ローダー王と協定を結ぶ役にはたつだろう」

小路からもと来た通りに引き返したところで、ベルガラスは暮れゆく空を見あげた。「急いだ方がよさそうだ」老人は言った。「城門が閉まる前に、この街を出るのだ。壁の外一マイルほどのところに馬をつないである」
「わざわざそのために引き返したんですか」シルクはSCOTT 咖啡機評測いささか驚いたような声で言った。
「むろんだとも。まさかモリンドランドまで歩いていくわけにはいかんからな」老人は川から離れた通りをすたすた歩いていった。
一行が城門にたどりついたのは、暮れゆく光の中で、衛兵たちが夜にそなえてまさに門を閉めようとしているときだった。ナドラク兵の一人が三人の行く手をさえぎるように手をあげかけた。だが途中で気が変わったらしく、小声でぶつぶつ罵りながら、行ってもいいと言わんばかりの仕草をした。タールを塗りたくった巨大な扉が、背後でドーンと音をたてて閉まった。続いて内側でかんぬきを下ろす音がして、重い鎖ががちゃがちゃ鳴った。門の上からのしかかるように見おろすトラクの彫刻面を、ガリオンは再び見あげてから、ゆっくりと背を向けた。
「追跡されている可能性はありますかね」シルクは街から続いている、ほこりまみれの街道を歩きながらベルガラスにたずねた。
「あり得ないことではないな」ベルガラスは答えた。「ドロスタ王はわれわれの行動の目的を知っているか、もしくは当たりをつけている。マロリー人のグロリムどもは実に油断のならん連中で、人の心をそれと気づかれずに探ることができるのだ。だからこそ王のちょっとした外出に、わざわざついてくる必要もないのだろう」
「何か手を打っておかなくていいんですか」しだいに暗くなってゆく空の下を歩きながら、シルクはたずねた。
「不用意な音をたてるには、いささかマロリーに近すぎるのでな」ベルガラ優思明スが言った。「遠く離れていようとゼダーにはわしの動きまわる音は聞こえるだろうし、トラクの眠りもほとんどまどろみ程度になっているだろう。よけいな物音をたててやつをうっかり起こすような危険は冒したくない」
一行は街を取りまく空き地をふちどるように続く、密集したやぶの黒い影に向かって街道を歩き続けた。川のそばの湿地で鳴くカエルのこえが、たそがれに響きわたった。
「それじゃ、トラクはもう眠っていないんだね」しばらくしてからガリオンが言った。かれはあわよくば眠っている神に忍びよって、不意打ちを食らわすことができるかもしれないという空しい希望を心のどこかで抱いていたのだ。
「眠ってなどおらん」かれの祖父は答えた。「おまえの手が〈珠〉にふれたとき、全世界を揺るがすほどの大きな音がしているのだ。あれを聞けばトラクとて、寝過ごしているわけにはいかんだろうよ。まだ本当に目覚めたわけではないが、まったく眠っているわけでもないのさ」
「そんなに大きな音がしたんですか」シルクがおもしろそうにたずねた。
「おそらく世界の反対側まで聞こえたことだろうよ。ところでわしはそこに馬を残しておいたのだが」老人、数百フィート離れた道路の左側の、影に閉ざされた柳の木立を指さした。
突然、かれらの背後で重い鎖ががちゃがちゃ鳴る音がして、カエルたちの声が一瞬やんだ。
「やつら、門を開けているぞ」シルクが言った。「公務上の理由がないかぎり、あんなことをするはずがない」
「さあ、急ぐのだ」ベルガラスが言った。
にわかに濃くなっていく闇の中で、さらさら音をたてる柳を三人がかきわけていく音を聞きつけた馬が、体を振るわせていなないた。一行は木立から馬を連れだし、乗りこむと再び街道へ引き返した。