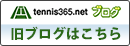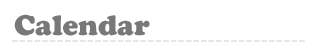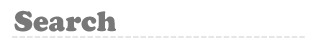——————–
空中のサーカス団 〜孤独な人形師〜
あの日、星が綺麗で僕は近所の必死に手を伸ばしていたのを覚えている。
幼かった僕の一番空に近い場所といえば、すべり台ぐらいしかなかった。
夏とはいえ、少し肌寒くて、空気が驚くほど澄んでいた。
気づくと、遠くの方から軽快な音楽が聞こえてきた。
この世のものとは思えない美しい音色と、陽気な雰囲気。
「レディースエーンドジェントルメーン!」
そんな明るい声が聞こえたと思うと、目の前に10代後半くらいの少年がヘンテコな帽子を被って立っていた。
「そこのチビ、ひとりなの?」
「おにぃちゃん、誰?」
「私かい?私は道化師フリーズ!空中の大サーカス『エア』の支配人さ!」
少年は遠くの三日月にお行儀よく、ちょこりと座った。
「おにぃちゃんは、ひとり?」
「ん?」
「ひとり?」
道化師のフリーズは初めて、道化の顔をやめて目を丸くした。
「何が、いいたいんだい?」
「僕が、独りぼっちだから」
その時の僕は毎晩喧嘩をする両親を見たくなくて、深夜1人家を抜け出していた。
星空だけが僕の支えだった。
「俺が独りかって?」
フリーズは僕の頭を乱暴にガシガシと掻き回した。
「大切な仲間が、いるんだ」
顔をあげた僕の目に映り込んだのは、満点の星空を見上げる美しい道化の顔だった。
***
喧しい目覚ましに不快感を覚えながら、布団から体を起こすと硬い何かが頭に当たった。
「いたっ…」
2段ベッドの天井で頭をぶつけたようだ。
「おーい、大丈夫かぁ?」
相棒のナイフ遣いスピアーが上のベッドから顔をのぞかせていった。
「なら、早く2段目を寄越せ」
「あぁ?やらねぇよ」
と、今度はゆっくりとベッドから出てきた僕の頭をパシンっと叩いた。
「顔洗いにいくぞ」
「うん」
ベッドの下から、革で出来た靴を引っ張り出して履いた。
外はいつものように明るい。のに、星がはっきりと見えた。
そんな朝の星空は、当たり前過ぎて目の端に映るだけだ。
昔のように焦がれたりしない。
もう、綺麗だとも思わない。
当然、お湯なんてない。冷たい水を頭から浴びて、長い前髪を掻きあげる。その髪を固めて、爪に装飾を施した。
キツめにサラシを巻いて、固めた髪に真っ赤なピンをバッテンにして留める。
鏡で己の姿を確認して、口元を指で釣り上げた。
「笑顔」
毎朝行っていることだ、何があっても笑っていなければ。大道芸を行うものとして、一番大切なことだ。
服装はいつもの練習着。顔にペイントをして、顔だけ本番。
朝礼。広場に皆が集まった。
「ロン、なんか格好ひどいぞ」
「いいんだ、いつものことだろ」
スピアーが僕を指さしていった。
「練習着に本番メイクって、なんか手抜きな感じだな」
「失礼な。本番メイクの練習だ」
「なんだそれ」
壇上で話をしていたフリーズがやって来ていった。
そのまま僕の髪を撫で回した。
「ボサボサ…」
「やったげる」
フリーズは手櫛で僕の髪を整え始めた。白くて細い指が素早く動く。
「一回しかやらないから、覚えろよ」
フリーズは優しくて、男の僕でも見蕩れるほどに美麗な顔立ちをしている。しかし、フリーズの顔には大きな手術の跡が残っていて、少し勿体無い。
あの日、フリーズは僕をこのサーカス団『エア』に連れてきた。
僕より頭一個ぶん高いフリーズを下から見上げる。
いつも笑っているフリーズの目は乾いている。冷たく濁っている。
今も。
「出来た。見てみ?」
「…すげ」
僕が見違えるほどの出来だった。あまりにも顔が出ていたので一瞬自分の顔が分からなかった。
「折角整った顔してんだからさ、もっと出しなよ」
「は、はい」
美人過ぎるフリーズにそんなこと言われても、逆に重い。
「似合っているよ、ロン」
「別人だね、ロン」
双子が僕の腰につかまり、交互に言った。
「…フェイク、フェイント。ありがとう」
二人はジャグリングをやる。時が止まったような、美しい演技をするのだ。
「ロン、こっち向いて」
「?はい」
「動かないでね」
と、フリーズは僕の髪に何かを差し込んだ。
「それ、あげる」
僕は頭に手を伸ばして、それに触れた。
星の飾りがついたピンだった。
フリーズがいつも身につけているものだ。
「これ、大切なものなんじゃ…」
「お守り」
フリーズはそれだけいうと、その場を離れていった。
***
あの夜、フリーズは優しく僕を持ち上げて抱きしめた。
寂しかったねって、僕を抱きしめた。
その時の僕はよく自分の気持ちが分からなかった。
ただ、僕を抱きしめながら泣くフリーズを見てやっと自覚したんだと思う。
そして、フリーズは言った。
「チビ、君の一番大事だと思うものはなんだい?」
僕と顔を合わせるようにしゃがんで、全てを見透かすように目をのぞき込んだ。
「お星様、綺麗なお星様が好き」
「いま、一番欲しいものは?」
「もの、じゃないんだけど…友だちがほしい」
フリーズは何を感じたのか優しく笑うと、強引に僕の頭を撫でた。
「おいで」
僕に手をのばしたフリーズは、また僕を優しく抱きしめた。
その瞬間から、空に浮かぶ星が「綺麗」だと思えなくなった。
「ろんー、ろーん!」
「え…?」
「どーした、ろんー。ぼーっとしてるぞー」
「え、あ、ウォーター。ごめん…」
水で出来た人形・ウォーターが、ペチペチと僕の顔を叩いた。
「しゅーちゅーしろーっ」
「ごめん、ごめん」
水が頬を滴るのを感じながら、銀色の細い指揮棒を握り直した。
「さあ、やろうか」
『おーー!』
ウォーター以外の人形達も声をあげた。
ファイア・アイス・ツリー・サンダー・リーフ・ライト・シルバー・ウェーブ。
人形達の顔を一体ずつ見て、腕を高らかに振り上げた。
同時に音楽が流れ出す。
その音楽に合わせて、人形達が踊り、音はどんどん大きくなる。
輪になった人形達の中からツリーという、木で出来た人形が歩き出した。
想像、集中。
笛の音と、太鼓のリズム。
聴け、音をよく聴け。
想像、集中、想像、集中。
指揮棒を天井につくかつかないかのギリギリのラインに投げる。
すると指揮棒だったものは、銀の美しい笛となって手元に戻ってきた。
シルバーが列に戻るのを見て、その笛を口に当てる。
音楽に違うテンポが加わり、人形達が違う隊列へと動き始める。
ツリーはその隊列には加わわらず、その場でクルクルと舞った。
ツリーが動くたんびに光の粒のようなものが散る。
集中…っ、今っ!
ツリーの動きがぴたりと止まったと思うと、ツリーの姿が見る見るうちに変わっていった。腕や足が伸びていき、大きな木製のメリーゴーランドを型どった。
で、できた!
と、一時の歓喜を押し殺して次の作業へ集中力を高める。
まだだ、もう少し…
口に当てていた笛を胸の前でバトンのように、廻した。
すると、シルバーがまた長い腕を笛に伸ばしはじめた。
笛は再び形を変え、5本のナイフに変わった。
そのナイフを正確にメリーゴーランドの方に素早く投げる。ここで外したら終わりだ。
ナイフ一本一本に人形達が集まっていくように…、全てを絡めながら。
ファイア・アイス・サンダー・リーフ・ライト・ウェーブが手を伸ばせれば…っ!。
「ロン!!」
「え?」
メリーゴーランドの方に投げたはずのナイフが僕に向かって飛んでくる。
ナイフの暴走!?
ナイフが僕に当たる寸前、大きな影が僕に被さった。
その影にナイフが突き刺さる感覚、振動が体にそのまま伝わってきた。
「フリーズ!フリーズがっ」
その影は、昔僕を守ってくれたフリーズだった。命の恩人のフリーズだった。
「ロン!何があった!
「スピアー!フリーズが、フリーズがっ…」
スピアー達が駆けつけた頃には、フリーズもうぐったりしていて、もうどうしたらいいのか分からなかった。
フリーズの血を浴びて、手足がガタガタ震える。指先すら十分に動かなくなってしまった。フリーズから止めどなく流れ出る血。その血で小さな溜まりが出来てきた。
僕は…なんてことを。僕は、僕は僕は僕は。
「ロン、落ち着け。人形達が不安がる」
「…あ」
そうだ、僕が不安定になると人形達も不安になってしまう。僕と人形達は感情だけで繋がっている。それが不安定になると、繋がりがぶれるのだ。
「そう、落ち着いて。とりあえずナイフを指揮棒に戻せ。このままじゃ出血が酷くなる」
「う、うん」
シルバーがまたトコトコと歩でて、僕の顔をのぞき込んだ。
「ろん?へいき?」
「うん、シルバー。もう少し、頑張ってね」
シルバーが目を閉じるとフリーズの肩や、腰、脇腹に刺さったナイフは細い元の指揮棒へと戻っていた。
医療士の「メス」が丁寧に傷口からそれを抜き、止血した。
「フリーズを医療室に運ぶの誰か手伝ってくれるか?」
では、と「スプレー」が手を上げ、華奢なフリーズの体を抱えて退場した。
「ごめんなさい…っ」
スピアーに慰めながら、僕は泣き続けた。
次の日の朝礼、フリーズは姿を現さなかった。
当たり前だ、3ヶ所もナイフが深く刺さったんだ。
メスが言うには、命に別状はないとのこと。でも、道化の仕事は当分出来ないだろう。と。
フリーズは道化の仕事がとても好きだった。真っ白な仮面を被って、沢山の人々を笑わせていられるのは幸せだと言っていた。
とんでもないことをしてしまった。その日、僕は練習を休んだ。
人形達の姿も見えない。
「ロン」
練習着のスピアーが僕のベッドに座って、そっと耳打ちした。
「今、メスが出張に出てる。フリーズに会うなら今だぞ」
「え」
珍しくスピアーが真顔だった。
「行ってこいよ」
スピアーに言われて、何を話せばいいのかも分からずにフリーズの病室の前に立っていた。
そんな大きな病棟ではない、プレハブのような物で粗末だ。
白い扉をトントンと叩き、ゆっくり内側に開いた。
「フリーズ…?」
フリーズは星の光が差し込む窓側、人形のように眠っていた。ベッドの周りには僕の人形達が集まっていた。
フリーズの寝顔は死んでいると言われれば信じてしまいそうなくらい、白く脆く消えてしまいそうだった。
「ロン」
フリーズが目を開いた。
「ロン、大丈夫?」
最初、何を言っているのか分からなかった。どうやら、僕に怪我はないか?と聞いているようだった。
自分がそんなナリになってしまっているというのに、どこまでも僕の心配をする。
冷たい顔立ちをしているくせに、人一倍優しくて温かい。
「フリーズ、ごめんなさい」
ベッドの横の古い椅子に座って、僕は言った。
「いいよ、俺なんて」
と、フリーズは儚げに笑った。
やっぱりフリーズはお人好しで、自分の事なんて全く考えていない。後回し、後回しなのだ。
窓の縁側には、フリーズの仮面とピンが置いてあった。
「エン、おいで」
フリーズがベッドの横をポンポンと叩いた。
その指定された場所にちょこんと座ると、フリーズは僕の頭を雑に撫で回した。
「ぅ…」
「ぁはは、エンはちっちゃいなぁ」
「ん?」
「初めてあった時と変わってない」
そんなにちっちゃいかな。
ちょっと気にしてなのに。
と、フリーズは徐ろに僕を抱きしめた。
初めて会ったあの夜のように優しく、大切なものを守るように。
「フリーズ…?」
「エン。エンに俺の仮面あげる」
「え?大事な商売道具でしょう?」
「んー…、そうなんだけど、もういいや」
「それ、どういうこと?」
フリーズは僕の質問に答えず、また頭を雑に撫で回した。
僕が最後に見たフリーズの顔は、幼く、年相応な心からの笑顔だった。
フリーズが姿を消して5年。
5年前のあの日、フリーズが初めて笑ったあの日の翌日、フリーズは姿を消した。
フリーズの病室には1枚のメモ。
『次期空中サーカス団・エアの支配人を人形師に任せる』
5年前、エアにいた人形師は僕だけだった。
「これでよかったのかな…」
「エン!出番だぜっ」
「すぐ行く!」
鏡の前で己を映し、口元を指で釣り上げる。
笑顔。
支配人のへんてこな帽子を被って、仮面を付ける。
「よし…っ」
舞台裏で、新人道化師の「レイン」の頭を撫でて、ライトアップされた舞台に上がる。
未だに慣れない歓声を全身に浴びながら、僕は笑顔で声を張り上げる。
「レディースエーンドジェントルメーン!」
フリーズに教えてもらった髪型、フリーズに貰った髪飾り、フリーズの仮面とフリーズに付けてもらった名前。
愛称は「エン」
本当の名前は誰も知らない。知っているのは僕とフリーズだけ。
孤独な人形師と冷笑する道化師の小さな世界。
頭上で起きるちょっとした出来事。
空中の物語。