「つかまってろよ」と指示すると、シルクは腕を伸ばして馬たちの尻を巧みに手綱でぴしゃりとたたいた。
荷馬車が上下にはね、走りだした馬たちのうしろで猛烈に揺れた。座席にしがみついて母乳餵哺いるガリオンの顔を寒風が痛いようにさした。
三台の荷馬車は全速力で次の谷をくだり、明かるい月光をあびた霜の野原と野原のあいだを疾走して、村とひとつだけともった明かりをあっというまにおきざりにした。
陽がのぼる頃にはたっぷり四リーグは進んでおり、シルクは手綱を引いて汗をかいて湯気をたてている馬たちをとめた。鉄のようにコチコチの道路をがむしゃらにとばしたせいで身体中が痛くなっていたガリオンは休息のチャンスにほっとした。シルクはかれに手綱をあずけて荷馬車からとびおり、ミスター?ウルフとポルおばさんのところへ歩いていくと、短い話をしてまた荷馬車に戻ってきた。「このすぐ先の小径にはいるんだ」指をもみながらガリオンに言った。
ガリオンは手綱をさしだした。
「やってごらん」シルクは言った。「手がかじかんじまったんだ。馬たちをただ歩かせりゃいい」
ガリオンは馬たちに声をかけて軽く手綱をゆらした。馬た嬰兒敏感ちはおとなしくまた進みだした。
「小径はぐるりと輪をかいてあの丘のうしろへ通しているんだ」両手をチュニックの中にひっこめているため、シルクは顎で方角を示した。「向こう側にはモミの木立がある。そこでとめて馬たちを休ませるんだ」
「ぼくたちはつけられていると思う?」ガリオンは訊いた。
「そいつをつきとめるには今が絶好のときなのさ」
一行は丘を一周して、道路と境を接する欝蒼たるモミ木立へ向かった。やがてガリオンは馬たちの向きを変え、木立の陰へ乗り入れた。
「これでよしと」シルクが荷馬車をおりて言った。「一緒においで」
「どこへ行くの?」
「後方のあの道をちょっと見たいんだ。木立をぬけて丘のてっぺんにのぼり、われわれの足跡が関心を中風治療ひくかどうか見てみるのさ」シルクは丘をのぼりはじめた。驚くべきはやさなのに、物音ひとつ立てずにのぼっていく。ガリオンは必死についていった。枯れ枝を踏みつけてさんざんヘマな音をたてたあげく、やっとガリオンにもコツがわかってきた。シルクはその調子だというように一度うなずいてみせたが、何も言わなかった。
木立は丘の手前で途切れており、シルクはそこで足をとめた。黒い道の通る下方の谷に人影はなかった。反対側の森からシカが二頭あらわれて、霜枯れの草をはみはじめただけだった。
「ちょっと待とう」シルクは言った。「ブリルとやつの手下が追ってくるとしたら、もうじきやってくるだろう」かれは切り株に腰をおろして、人気《ひとけ》のない谷を見守った。
しばらくして二輪荷馬車が一台、ウィノルドの方角へゆっくり道を進んでいった。遠ざかるにつれて豆粒のようになったが、傷跡のような道を行く速度はばかにのろく思われた。
太陽の位置が少し高くなり、かれらはまぶしい朝日の中で細めた目をこらした。
「シルク」ガリオンはとうとうためらいがちに言った。
「なんだ、ガリオン?」
「これはどういうことなの?」大胆な質問だったが、ガリオンはそう訊いてもかまわないほどシルクとはもう気心が知れているような気がした。
「どういうこととは?」
「ぼくたちのしていることさ。すこしは聞いたし、推測もちょっとはしてみたけど、ぼくには本当になにがなんだかわからないんだ」
「どんな推測をした、ガリオン?」シルクは訊いた。ひげもじゃの顔の中で小さな目が明かるすぎるほどだった。
「なにかが盗まれて――なにかすごく大事なものなんだ――ミスター?ウルフとポルおばさん――それに残りのぼくたち――がそれを取り返そうとしている」
「ふむ。そのとおりだよ」
「ミスター?ウルフとポルおばさんは見かけと全然ちがう人たちなんだ」ガリオンはつづけた。
「そう。ちがう」シルクは同意した。
「かれらは他人にはできないことができるんだと思う」ガリオンは言葉を捜しながら言った。
「ミスター?ウルフは見ないでもこのなにか――それがなんだろうと――を追いかけることができる。それから、先週あの森の中でマーゴ人たちが通りすぎたとき、かれらはなにかをしたんだ――どう説明したらいいのかわからないけど、まるで手を伸ばして、ぼくの頭を眠らせたみたいだった。どうやってやったんだろう? それにどうして?」
シルクはくすくす笑った。「きみはじつに観察眼のするどい若者だ」と言ってから、もっと真剣な口調になって、「われわれは由々しき時代に生きているんだ、ガリオン。一千年、いやそれ以上の歳月の出来事がすべてこの時代に焦点を合わせている。世界はそういうものらしい。なにこともなく数世紀がすぎるかと思うと、短い数年間に世界が二度と元通りにはならないようなきわめて重大な出来事が起きるんだ」
「選択権があるなら、ぼくはそっちの波乱のない数世紀のほうがいいな」ガリオンはむっつりと言った。
「よせよ」シルクの唇がめくれてイタチのような笑いがうかんだ。「今こそ活動のときだぞ――一切が起きるのを見て、その一端をになうときだ。血わき肉おどる冒険じゃないか」
ガリオンはそれを聞き流した。「ぼくたちが追っているものってなんなの?」
シルクは神妙に言った。「それの名前とか、それを盗んだ者の名前については知らないのが一番いい。われわれをはばもうとしている連中がいるんだ。知らなけりゃ、あらわしようがないからな」
「マーゴ人たちにぺらぺらしゃべる習慣なんかぼくにはないよ」ガリオンはぎごちなく言った。
「やつらにしゃべる必要はない。連中の中には手を伸ばして人の頭から思考をつかみだせる者がいるんだ」
「そんなことありえないよ」
「なにが可能でなにが不可能かだれにわかる?」シルクは言った。ガリオンは一度ミスター?ウルフと可能と不可能について話しあったことを思いだした。
シルクはのぼったばかりの太陽をうけて切株に坐り、まだ薄暗い谷を思案顔に見おろしていた。ありふれたチュニックにズボンをはき、粗織りの茶色いケープについた頭巾をかぶったその姿は、どこにでもいる平凡な小男だった。「きみはセンダー人として育てられただろう、ガリオン」かれは言った。「センダー人というのは堅実で実際的な人々だ。魔法とか魔術とかいった日に見えない、自分の手でたしかめられないものにはまずがまんができない。きみの友だちのダーニクは完壁なセンダー人だ。かれは靴の修繕や壊れた車輪の修理、病気の馬に薬をのませることは得意でも、ほんのちょっとした魔法ですら信じようとはしないだろう」
「ぼくだってセンダー人だ」ガリオンは抗議した。シルクのそれとない言いまわしが、自分はセンダー人だというガリオンの意識の核心を脅した。
シルクはふり向いてじっとガリオンを見つめた。「そうじゃない。きみはちがう。センダー人は見ればわかる――アレンド人い、あるいはチェレク人とアルガー人のちがいがわかるようにな。センダー人には一定の頭の恰好、一定の目つきがあるが、きみにはそれがない。きみはセンダー人じゃない」
「じゃあ何人なのさ?」ガリオンは挑むように言った。
「それがわからないんだ」シルクは困惑ぎみに額にしわをよせた。「何人かすぐ見抜けるように訓練をつんできたわたしにわからないんだから、こいつはきわめてまれなことなんだ。まあ、そのうちわかるかもしれんがね」
「ポルおばさんはセンダー人?」
-
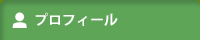
-
-

-

- 未分類 (28)
-

-

-

-



