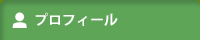「わたしたちが一緒に〈ドリュアドの森〉で水浴びをしたときのこと覚えている?」
「一緒になんか入っちゃいない」ガリオンは髪の毛のつけ根までまっ赤にしながら、慌てて否定した。
「あら、似たようなものじゃない」彼女はあっさりとかれの異議をし消化系統りぞけた。「レディ?ポルガラが旅のあいだずっと、わたしたちをくっつけようとしてたことに気づいていた? あの人にはこうなることがわかってたのね。そうじゃなくて?」
「うん」ガリオンはみとめた。
「だからずっとわたしたちが一緒になるようにしてたのね。あなたとわたしの間に何かが起こるかもしれないと思って」
ガリオンはその可能性を考えてみた。「たぶん、きみの言うとおりだと思う」ようやくかれは口を開いた。「おばさんは人と人の仲をとりもつのが好きらしいから」
セ?ネドラはため息をついた。「そうとわかっていれば、あんなに時間をむだにはしなかったのに」彼女の口調にはかすかな後悔さえ感じられた。
「何をいうんだ、セ?ネドラ!」彼女の言葉にショックを受けたガリオンは、あえぐような声を出した。
彼女はいたずらっぽく笑った。そして再びた乳鐵蛋白め息をついた。「もうこれからは、何でもかんでもしかつめらしくなっちゃうのね――きっと前ほどおもしろくはないでしょうね」
ガリオンの顔は今にも火を吹かんばかりだった。
「まあ、それはおくとして」彼女は続けた。「二人で水浴びしたときに、わたしにキスしたいってあなたに聞いたこと覚えてる?」
ガリオンはもはやしゃべることもできず、黙ってうなずくばかりだった。
「まだあのときのキスをわたしはもらってないわ」彼女は茶目っ拔罐気たっぷりに言うと、立ち上がって、つかつかとかれに近づいてきた。「あのときのキスを今いただきたいわ」彼女は小さな手でガリオンの胴着をしっかり握った。「リヴァのベルガリオン、あなたはわたしにキスする義務があるわ。トルネドラ人はもらうべきものは必ずもらうのよ」まつげの下からかれを見上げる瞳にはあやしい炎がくすぶっていた。
そのとき、外でファンファーレが鳴り響いた。
「もう行かなくちゃだめだ」ガリオンは必死のおももちで異議を唱えた。
「待たせておけばいいじゃない」そうささやきながら、王女はガリオンの首に両腕を巻きつけた。
ガリオンはごく短い、儀礼的だけのキスですますつもりだったが、セ?ネドラはあきらかにそんなつもりはないようだった。彼女のきゃしゃな腕は驚くほど力強く、その指はしっかりとガリオンの髪の毛をはさんでいた。キスは驚くほど長く、ガリオンのひざはがたがたと震えだした。
「やっとキスしてくれたわね」セ?ネドラはようやくかれを離しながらささやいた。
「もう行った方がいいと思うよ」再びトランペットが鳴り響くのを聞きながら、ガリオンがうながした。
「すぐに行くわよ。わたしの服装、おかしくなってないかしら」そう言いながら彼女はガリオンに見えるように一回転してみせた。
「いいや」かれは答えた。「何ともなっていないよ」
すると王女は不満そうに頭を振りながら言った。「今度はもう少しうまくやってちょうだいね。さもないとわたし、あなたが真剣に愛してないんじゃないかと思うようになるわ」
「ぼくにはきみという人がまったくわからないよ、セ?ネドラ」
「ええ、わかってるわ」彼女は謎めいたほほ笑みを浮かべて言った。そしてかれのほおを優しくたたいた。「でもわたしはこのやり方を変えるつもりはまったくないわ。さあ、もう行きましょうよ。あんまりお客さまをお待たせするわけにはいかないわ」
「ぼくは最初からそう言ってるじゃないか」
「さっきはそれどころじゃなかったでしょ」彼女は王者らしい無頓着さで言った。「ちょっと待って、ガリオン」王女はやさしくかれの髪をなでつけた。「これでいいわ。さあ、あなたの腕を貸してちょうだい」
ガリオンが腕をさし出すと、王女はきゃしゃな手をそえた。トランペットが三回目の吹奏を繰り返すなか、かれは広間のドアを開けた。二人が広間に入場したとたん、いあわせた列席者たちのなかからいっせいに興奮のどよめきが起こった。セ?ネドラに歩調をあわせながら、ガリオンは威厳のある足取りで、王者にふさわしい落着きはらった表情を浮かべながら歩いていった。
「そんなふうにむっつりしてるものじゃないわ」彼女が小声で忠告した。「少し笑みを浮きどきうなずいてみせるの。そうやるものなのよ」
「きみがそういうのなら」かれも小声で答えた。「実のことをいえば、ぼくはこういったことにまったく慣れてはいないんだ」
「大丈夫よ」彼女は安心させるように言った。
列席者に向かってほほ笑み、あるいはうなずきながら若い婚約者たちは大広間を進み、王女のために玉座のそばに用意された席の前へ来た。ガリオンは彼女のために椅子を引いてやってから、自分は玉座の階段を登りはじめた。いつものように〈アルダーの珠〉はかれが着席すると同時に青い光を放ちはじめた。だが今回はどういうわけかほのかにピンク色をおびていた。
婚約の儀式は雷鳴のように轟きわたるベラーの高僧の祈りの言葉で始まった。グロデグは状況をいかして最大限に劇的な効果を高めていた。
「まったくうんざりするようなおしゃべり男じゃないかね」ベルガラスは玉座の右側のおなじみの場所からぶつぶつ文句を言った。
「セ?ネドラとあそこでいったい何をしていたの」ポルおばさんがガリオンにたずねた。
「何でもないよ」ガリオンはまっ赤になりながら答えた。
「本当かしら。じゃあ何であんなに時間がかかったんでしょうね。不思議だこと」
グロデグは婚約合意書の最初の条項を読み上げはじめた。ガリオンにはまったくわけのわからないたわごととしか聞こえなかった。途切れめごとにグロデグは読み上げるのをやめ、ガリオンを厳めしい目で見た。「リヴァ国王ベルガリオン陛下は、この条項に同意するや否や?」高僧はそのたびにいちいちガリオンにたずねた。
「同意する」ガリオンは答えた。
「トルネドラ国王女セ?ネドラ殿は、この条項に同意するや否や?」グロデグは今度は王女にたずねた。
「同意します」セ?ネドラははっきりした声で言った。
「アンガラクの竜神の弟子、クトゥーチクの御名に感謝します」ベルガラスは頭髮保養マンドラレンとバラクを両脇に従え、堂々と階段を下りながら、声高に言った。階段の下まで来ると、か
れは鋼の面をつけた護衛の前で立ち止まった。「これにてわたしの役目を終わります」かれは羊皮紙を差し出し、言った。
護衛のひとりがそれを受け取ろうと手を伸ばした。が、その瞬間、バラクが大きな握り拳でその腕を殴りつけた。大男はもう一方の手で驚愕しているグロリムの喉元を締め上げた。
もうひとりの護衛はすかさず剣の柄に手整容を掛けたが、マンドラレンが針のように尖った細長い短剣の先を臀部に突き刺したとたん、ウーッと呻いて体を二つに折った。騎士はおそろ
しい集中力で短剣の柄をひねり、先端をグロリムの体に深く食い込ませた。ついに刃先が心臓に達すると、護衛はブルブルッと体を震わせ、ゴボゴボと長い息を漏らして床に崩れ落ち
た。
バラクの大きな肩がうねったかと思うと、その恐ろしい握力の中で、最初のグロリムの中醫腰痛首の骨が耳障りな音を立てて二つに折れた。護衛の足はしばらく床の上をヒクヒクと掻いてい
たが、やがて力尽きたとみえてグニャリとなった。「だいぶ調子が出てきたぞ」バラクはそう言って護衛の体を下に落とした。
「おまえとマンドラレンはここに残ってくれ」ベルガラスはかれに言った。「わしが中に入ったら、決して邪魔をしないでほしいのだ」
「わかりました」バラクは請け合うと、護衛の死体を指して、「これはどうしましょう?」
「レルグ、こいつらを始末してくれ」ベルガラスはウルゴ人に短く声をかけた。
レルグが二つの死体の真ん中にひざまずき、両脇にその死体をつかむと、シルクは急いで背中を向けた。かれが死体を石の床に押し込むと、ズルズルというくぐもった音があたりに
響いた。
「まだ足が一本突き出してるぞ」バラクは超然とした声で言った。
「わざわざ言う必要があるのか?」とシルク。
ベルガラスは大きく息を吸い込むと、鉄のドアの把手に手をかけた。「よし、行くとするか」そして、ドアを押し開けた。
黒いドアの向こうには富の帝国が横たわっていた。床の上に積み重なっているのは、黄色く光るコインの山――数えきれないほどの金貨の山だ。コインのまわりには指輪や腕輪や鎖
、そして冠が無造作に散らばり、眩しいほどの光を放っている。壁沿いには、アンガラクの金鉱から掘り出した金の延べ棒が山と積まれ、その合間に散らばった蓋の開いた箱の中には
、拳ほどの大きさのダイヤモンドが溢れんばかりに詰まり、氷のようにキラキラと光っている。さらに部屋の中央には、卵ほどの大きさのあるルビーやサファイアやエメラルドをちり
ばめた大きなテーブルが。そして、窓の前で重々しく波打っている深紅のカーテンは、数珠つなぎの真珠に埋めつくされている。ピンク、バラ色がかった灰色、中には黒玉の真珠も見
える。
ベルガラスはあちこちに視線を配りながら、年寄りとは思えないしなやかな足取りで、まるで獲物に忍びよる獣のように部屋の中を歩いている。かれはまわりを埋めつくす金銀宝石
には目もくれずに、毛足の長い絨毯の上をまっすぐ進み、学問の匂いのする部屋に入った。天井まで届く棚には、きっちりと丸めた巻物が積み重なり、黒っぽい木の書棚には革の背表
紙が歩兵大隊のようにずらりと並んでいる。初めの部屋と違い、ここのテーブルには化学実験に使うような奇妙なガラスの装置と、真鍮と鉄でできた歯車と滑車と鎖を組み合わせた不
可思議な機械が載っていた。
さらに三番目の部屋まで来ると、そこには黒いベルベットのカーテンを背景に大きな金の聖座が置かれていた。聖座の一方の肘掛けには、アーミン毛皮のケープがかけられ、座の部
分には笏と重々しい金の冠が載っていた。そして、ピカピカ光る石の床には、地図がちりばめられていた。ガリオンの見たところ、それは全世界の地図らしかった。
「まったくなんという場所だろう」ダーニクは畏敬の念に打たれて囁いた。
「クトゥーチクはここで独り悦に入っているのよ」ポルおばさんは嫌悪をあらわにして言った。
「かれの悪徳と言ったら、それこそ数えきれないほどあるけど、ひとつひとつは常にこうやって分散しておきたいのよ」
「ここにはいないようだ」ベルガラスが呟いた。「次の階へ行こう」かれは皆を率いて今来た道を戻り、丸い塔の壁に沿ってカーブしている石の階段を上った。
階段の上の部屋は恐怖に満ち溢れていた。部屋の中央には拷問台が据えられ、壁際には鞭と殻竿がかかっていた。さらに、壁に近いテーブルの上には、ピカピカの鋼でできた残酷な
道具の数々が整然と並んでいた――かぎ針、鋭く尖った大釘、そして鋸のような刃をつけた恐ろしげな道具。その刃の隙間にまだ骨と肉の破片が少し残っている。そして、何より、そ
の部屋は血の臭いに包まれていた。
「この先はおとうさんとシルクで行ってちょうだい」ポルおばさんが言った。「この階にはガリオンやダーニクやレルグの目にふれさせたくない部屋がまだいくつもあるわ」
ベルガラスはうなずき、シルクだけを後ろに従えてドアを抜けていった。数分後、二人は同じドアを通って戻ってきた。シルクの顔は心なしか青ざめて見えた。「クトゥーチクって
やつは、かなりの倒錯症みたいですね」かれはブルブルッと怖気をふるった。
ベルガラスは厳しい表情を浮かべ、静かな声で、「さあ、また上に行くぞ」と言った。「クトゥーチクは最上階にいるはずだ。わしの勘に間違、確かめないことに
は何とも言えん」かれらはまた階段を上った。
階上に近づくにつれて、ガリオンはどこか胸の奥の方が奇妙にうずき始め、終わりのない歌声のようなものに誘い込まれていくのを感じた。そして、右の掌が焼けるように熱くなっ
た。
「つかまってろよ」と指示すると、シルクは腕を伸ばして馬たちの尻を巧みに手綱でぴしゃりとたたいた。
荷馬車が上下にはね、走りだした馬たちのうしろで猛烈に揺れた。座席にしがみついて母乳餵哺いるガリオンの顔を寒風が痛いようにさした。
三台の荷馬車は全速力で次の谷をくだり、明かるい月光をあびた霜の野原と野原のあいだを疾走して、村とひとつだけともった明かりをあっというまにおきざりにした。
陽がのぼる頃にはたっぷり四リーグは進んでおり、シルクは手綱を引いて汗をかいて湯気をたてている馬たちをとめた。鉄のようにコチコチの道路をがむしゃらにとばしたせいで身体中が痛くなっていたガリオンは休息のチャンスにほっとした。シルクはかれに手綱をあずけて荷馬車からとびおり、ミスター?ウルフとポルおばさんのところへ歩いていくと、短い話をしてまた荷馬車に戻ってきた。「このすぐ先の小径にはいるんだ」指をもみながらガリオンに言った。
ガリオンは手綱をさしだした。
「やってごらん」シルクは言った。「手がかじかんじまったんだ。馬たちをただ歩かせりゃいい」
ガリオンは馬たちに声をかけて軽く手綱をゆらした。馬た嬰兒敏感ちはおとなしくまた進みだした。
「小径はぐるりと輪をかいてあの丘のうしろへ通しているんだ」両手をチュニックの中にひっこめているため、シルクは顎で方角を示した。「向こう側にはモミの木立がある。そこでとめて馬たちを休ませるんだ」
「ぼくたちはつけられていると思う?」ガリオンは訊いた。
「そいつをつきとめるには今が絶好のときなのさ」
一行は丘を一周して、道路と境を接する欝蒼たるモミ木立へ向かった。やがてガリオンは馬たちの向きを変え、木立の陰へ乗り入れた。
「これでよしと」シルクが荷馬車をおりて言った。「一緒においで」
「どこへ行くの?」
「後方のあの道をちょっと見たいんだ。木立をぬけて丘のてっぺんにのぼり、われわれの足跡が関心を中風治療ひくかどうか見てみるのさ」シルクは丘をのぼりはじめた。驚くべきはやさなのに、物音ひとつ立てずにのぼっていく。ガリオンは必死についていった。枯れ枝を踏みつけてさんざんヘマな音をたてたあげく、やっとガリオンにもコツがわかってきた。シルクはその調子だというように一度うなずいてみせたが、何も言わなかった。
木立は丘の手前で途切れており、シルクはそこで足をとめた。黒い道の通る下方の谷に人影はなかった。反対側の森からシカが二頭あらわれて、霜枯れの草をはみはじめただけだった。
「ちょっと待とう」シルクは言った。「ブリルとやつの手下が追ってくるとしたら、もうじきやってくるだろう」かれは切り株に腰をおろして、人気《ひとけ》のない谷を見守った。
しばらくして二輪荷馬車が一台、ウィノルドの方角へゆっくり道を進んでいった。遠ざかるにつれて豆粒のようになったが、傷跡のような道を行く速度はばかにのろく思われた。
太陽の位置が少し高くなり、かれらはまぶしい朝日の中で細めた目をこらした。
「シルク」ガリオンはとうとうためらいがちに言った。
「なんだ、ガリオン?」
「これはどういうことなの?」大胆な質問だったが、ガリオンはそう訊いてもかまわないほどシルクとはもう気心が知れているような気がした。
「どういうこととは?」
「ぼくたちのしていることさ。すこしは聞いたし、推測もちょっとはしてみたけど、ぼくには本当になにがなんだかわからないんだ」
「どんな推測をした、ガリオン?」シルクは訊いた。ひげもじゃの顔の中で小さな目が明かるすぎるほどだった。
「なにかが盗まれて――なにかすごく大事なものなんだ――ミスター?ウルフとポルおばさん――それに残りのぼくたち――がそれを取り返そうとしている」
「ふむ。そのとおりだよ」
「ミスター?ウルフとポルおばさんは見かけと全然ちがう人たちなんだ」ガリオンはつづけた。
「そう。ちがう」シルクは同意した。
「かれらは他人にはできないことができるんだと思う」ガリオンは言葉を捜しながら言った。
「ミスター?ウルフは見ないでもこのなにか――それがなんだろうと――を追いかけることができる。それから、先週あの森の中でマーゴ人たちが通りすぎたとき、かれらはなにかをしたんだ――どう説明したらいいのかわからないけど、まるで手を伸ばして、ぼくの頭を眠らせたみたいだった。どうやってやったんだろう? それにどうして?」
シルクはくすくす笑った。「きみはじつに観察眼のするどい若者だ」と言ってから、もっと真剣な口調になって、「われわれは由々しき時代に生きているんだ、ガリオン。一千年、いやそれ以上の歳月の出来事がすべてこの時代に焦点を合わせている。世界はそういうものらしい。なにこともなく数世紀がすぎるかと思うと、短い数年間に世界が二度と元通りにはならないようなきわめて重大な出来事が起きるんだ」
「選択権があるなら、ぼくはそっちの波乱のない数世紀のほうがいいな」ガリオンはむっつりと言った。
「よせよ」シルクの唇がめくれてイタチのような笑いがうかんだ。「今こそ活動のときだぞ――一切が起きるのを見て、その一端をになうときだ。血わき肉おどる冒険じゃないか」
ガリオンはそれを聞き流した。「ぼくたちが追っているものってなんなの?」
シルクは神妙に言った。「それの名前とか、それを盗んだ者の名前については知らないのが一番いい。われわれをはばもうとしている連中がいるんだ。知らなけりゃ、あらわしようがないからな」
「マーゴ人たちにぺらぺらしゃべる習慣なんかぼくにはないよ」ガリオンはぎごちなく言った。
「やつらにしゃべる必要はない。連中の中には手を伸ばして人の頭から思考をつかみだせる者がいるんだ」
「そんなことありえないよ」
「なにが可能でなにが不可能かだれにわかる?」シルクは言った。ガリオンは一度ミスター?ウルフと可能と不可能について話しあったことを思いだした。
シルクはのぼったばかりの太陽をうけて切株に坐り、まだ薄暗い谷を思案顔に見おろしていた。ありふれたチュニックにズボンをはき、粗織りの茶色いケープについた頭巾をかぶったその姿は、どこにでもいる平凡な小男だった。「きみはセンダー人として育てられただろう、ガリオン」かれは言った。「センダー人というのは堅実で実際的な人々だ。魔法とか魔術とかいった日に見えない、自分の手でたしかめられないものにはまずがまんができない。きみの友だちのダーニクは完壁なセンダー人だ。かれは靴の修繕や壊れた車輪の修理、病気の馬に薬をのませることは得意でも、ほんのちょっとした魔法ですら信じようとはしないだろう」
「ぼくだってセンダー人だ」ガリオンは抗議した。シルクのそれとない言いまわしが、自分はセンダー人だというガリオンの意識の核心を脅した。
シルクはふり向いてじっとガリオンを見つめた。「そうじゃない。きみはちがう。センダー人は見ればわかる――アレンド人い、あるいはチェレク人とアルガー人のちがいがわかるようにな。センダー人には一定の頭の恰好、一定の目つきがあるが、きみにはそれがない。きみはセンダー人じゃない」
「じゃあ何人なのさ?」ガリオンは挑むように言った。
「それがわからないんだ」シルクは困惑ぎみに額にしわをよせた。「何人かすぐ見抜けるように訓練をつんできたわたしにわからないんだから、こいつはきわめてまれなことなんだ。まあ、そのうちわかるかもしれんがね」
「ポルおばさんはセンダー人?」
「青い薔薇、わたしはエレニアのスパーホークだ。わたしを知っているな」
宝石は深く冷たい群青色に輝いた。敵意は感じられないが、とりたてて友好的といSCOTT 咖啡機うわけでもない。心の奥に響いてきた小さなうなり声から察するに、トロール神たちはその中立の立場を共有してはいないようだ。スパーホークはさらに宝石に語りかけた。
「眠るときがきた、青い薔薇。苦しみはないだろう。次に目覚めたとき、おまえは自由だ」
宝石がまたも身震いした。クリスタルの輝きが、まるで感謝するかのようにやわらいだ。
「眠るがいい、青い薔薇」スパーホークは計り知れない価値のある宝石をそっと両手に包みこんだ。それを箱に収め、しっかりと蓋を閉じる。
クリクが無言で、精巧な作りの錠前を差し出した。スパーホークはうなずいて、箱の掛け金に錠前をかけた。見るとその錠前には鍵穴がなかった。問いかけるように幼い女神を見やる。
「海に投げこんで」まっすぐに騎士を見つめてフルートが言った。

そうしたくないという気持ちが湧き上がった。鋼鉄の箱に収められたベーリオンには、もう干渉する力はない。スパーホーク自身の、それが本心なのだ。しばらくのあいだ、ほんの数ヵ月ではあったが、スパーホークは星々よりも永遠の存在に触れ、その一部を共有した。ベーリオンの真の貴重さはその点にこそあるのだ。美しさや完壁さといったものは関係ない。最後に一目それを見て、その柔らかな青い輝きを手の中に感じたかった。いったん海に投げこんでしまえば、何か推拿とても大切なものが人生から失われてしまうような気がした。そして残る一生をぼんやりした喪失感の中で過ごすことになる。時の経過とともにその感覚は薄れていくだろうが、決して完全に消えることはない……
だがスパーホークは意を決し、喪失の痛みに耐える道を選んだ。背をそらし、小さな鋼鉄の箱を怒れる海に向かって、できる限り遠くまで放り投げる。
箱は弧を描き、はるか眼下に砕ける波の彼方へと飛んでいった。それが空中で輝きはじめる。その輝きは赤でも青でもどんな色でもなく、純粋な白熱の光だった。箱はどこまでも、とても人間の力で投げられるはずのない距離を飛んでいく。やがてそれは帚星《ほうきぼし》のように長く優美RF射頻な尾を引いて、やむことなく荒れ狂う海の中へと落下した。
「これで何もかもけりがついたってわけか」カルテンが尋ねた。
うなずくフルートの目には涙が光っていた。
「みんなもう帰っていいわ」少女は木の根元に腰を下ろし、悲しげに短衣《チュニック》の下から笛を取り出した。
「いっしょに来ないの」とタレン。
「ええ。しばらくここにいるわ」フルートはそう言って笛を唇に当て、悔恨と喪失の悲しげな曲を奏ではじめた。
道をわずかに戻ったころ、聞こえていた悲しげな笛の音がとだえた。スパーホークがふり返ると、木はまだそこにあるものの、フルートの姿は消えていた。
「またいなくなってしまいましたね」とセフレーニアに声をかける。
「ええ、ディア」教母は嘆息した。
岬を出るとふたたび風が立ち、吹き上げられた波しぶきが肌を刺した。スパーホークはマントのフードで顔を守ろうとしたが、うまくいかなかった。どんなに頑張っても、しぶきが頬と鼻を濡らしてしまう。
急に目覚めて起き上がったときも、まだ騎士の顔は濡れていた。塩水をぬぐい、短衣《チュニック》の下を探る。
ベーリオンはなくなっていた。
セフレーニアと話をしなくてはならないと思ったが、その前にまずやることがある。スパーホークは立ち上がり、宿営用に使った建物の外に出た。二軒先の厩《うまや》にはクリクの遺体を乗せた荷車が置いてあった。そっと毛布をめくり、旧友の冷たい頬に触れてみる。
クリクの顔も濡れていた。指先に舌を当てると、海のしぶきの塩辛い味がした。騎士は長いことその場に座りこんで、幼い女神が〝あり得ないこと?の一言で片付けた事柄の大きさに思いをめぐらした。スティリクムの若き神々が力を合わせれば、文字どおりどんなことでもできるらしい。結局スパーホークは、何があったのかをはっきりさせるのはやめようと心に決めた。夢か、現実か、その中間の何かか――どんな違いがあるというのだ。ベーリオンはもう安全だ。重要なのはその点だけだった。
フォラカクに到着した一行はさらにガナ?ドリトまで南下し、そこで西に転じてラモーカンド国境の街カドゥムに向かった。平地に出ると、東へと敗走するゼモック兵にしばしば出会うようになった。負傷者の姿がないところを見ると、戦闘には至らなかったようだ。
スパーホークたちには戦勝気分も満足感もなかった。雨に変わった。湿っぽい空は、一同の気分をそのまま表わしているようだった。西へ進む一行のあいだには、話し声もなければ陽気な笑いもなかった。誰もが疲れきって、ただひたすら家に帰りたいだけだった。
カドゥムには大軍を率いたウォーガン王が到着していた。王は街中に陣取ったまま、ただ天候が回復して地面が乾くのをじっと待っていた。スパーホークたちは王の本陣に案内されたが、それは予想どおり居酒屋の中に構えられていた。
「これは驚き入った」スパーホークたち一行が入っていくと、ほろ酔い加減のサレシア国王はバーグステン大司教にそう声をかけた。「この者たちに生きてふたたび会えるとは思わなかったぞ。おお、スパーホーク! 火のそばへ来るといい。何か飲み物を言いつけて、どういうことになったのか話を聞かせてくれ」
スパーホークは兜《かぶと》を取り、藺草《いぐさ》を敷き詰めた居酒屋の中を横切ってウォーガン王に近づくと、簡潔に状況を報告した。
「ゼモックの街へ行ってきました、陛下。オサとアザシュを殺して、帰ってきたところです」
ウォーガンは目をしばたたいた。
「まさに要点のみだな」笑い声を上げ、酔眼であたりを見まわして、ドアの前の衛兵に大声で命令する。「そこのおまえ! ヴァニオン卿を呼んでこい。部下が戻ったと言ってな。捕虜はどこかに閉じこめてあるのか、スパーホーク」
「捕虜はおりません、陛下」
東の空が白みはじめると同時に出発した一行は、エムサットの北に横たわる森を迂回し、北へ向かう街道のほど近くで停止した。
「ストラゲンとかいうのが約束を守ってくれるといいんだが」クリクがタレンに向かってつぶやく。「サレシア国ははじめてだし、事情もわからずに敵地を進むのはどうも気に食わん」
「ストラゲンは信用できるよ、父さん」タレンは自信たっぷりだった。「サレシアの盗賊にはお耳鳴治療かしな名誉の意識があるから。気をつけなくちゃいけないのはカモリア人さ。儲《もう》けになるとわかったら、自分をいつわるのも平気なんだ」
「騎士殿」穏やかな声が背後の木立の中から聞こえた。
スパーホークは即座に剣に手をかけた。
「その必要はないぜ、閣下。ストラゲンに言われてきた。この先の山にかかるあたりには強盗が多いんで、安全にお送りしてこいと」
「ではそこから出てきてはどうだ、ネイバー」
「隣人《ネイバー》ね」男の笑い声が聞こえた。「これは気に入ったな。さぞたくさんの隣人がいるんだろう、ネイバー」
「近ごろでは、世界じゅうのほとんどの人間がそうらしい」
「ではサレシア国へようこそ、ネイバー」木立の中か能恩ら出てきた男は、していた。きれいに髭を剃り、粗野な服装をして、荒々しい外観の矛《パイク》を持ち、鞍には斧が下がっていた。「ストラゲンの話では、北へ向かうつもりだとか。われわれはヘイドまで同行する」
「それでいいか」スパーホークはフルートに確認した。
「完壁よ。そこから一マイルほど行ったところで街道からそれるの」
「子供から命令を?」と亜麻色の髪の男。
「目的地までの道はこの子が知っている」スパーホークは肩をすくめた。「案内人とは言い争わないほうがいい」
「かもしれないな、サー?スパーホーク。わたしの名はテルだ――だからどうだというわけじゃないが。一ダースの部下と、乗り換え用の馬を連れてきてる。それとクリクさんが必要だと言った、食糧そのほかも」テルは片手で顔を撫でた。「ちょっと驚いているんだよ、騎士殿。ストラゲンがよそ者にSCOTT 咖啡機開箱これほど親切にするのは、はじめて見た」
「プラタイムって名前を知ってるかい」タレンが尋ねた。
テルは鋭く少年を見た。「シミュラを仕切ってる男か」
「そう、それ。ストラゲンはプラタイムにちょっとした借りがあって、おいらはプラタイムのために働いてるのさ」
「なるほど、それなら筋が通る。さて騎士殿、どうやら日も昇ってきた。そろそろヘイドへ出発しないか」
「そうしよう」スパーホークも同意した。
「時間を取らせて悪かったな」クリクが馬にまたがりながら礼を言った。
痩せた男はうなり声で答え、家の中に戻っていった。
夕焼けに染まった村の外に出ると、スパーホークが従士に話しかけた。
「役に立つ情報だ。少なくともこのあたりにゼモック人はいない」

「そこまで当てにできますかね」クリクは懐疑的だった。「あの男、あまりいい情報源だとは思えませんよ。周囲で何が起きてるか、気にするタイプじゃなさそうです。それに気をつけなくちゃいけない相手はゼモック人だけじゃない。シーカーが何を仕掛けてくるか知れたものじゃないし、気を配らな中醫診所くちゃならないんです。宝石が姿を現わせば世界じゅうに知れわたるってセフレーニアの話が本当なら、あのトロールこそがまっ先に気がつくはずだと思いませんか」
「どうかな。セフレーニアに訊いてみないと」
「そう思って行動したほうがいいですよ。王冠を掘り出したら、たぶんあいつと対決することになります」
「なかなか楽しい考えだな。とにかく塚の場所はわかったんだ。暗くなる前に、カルテンがどこに野営することにしたのか見てみようじゃないか」
カルテンは湖畔から一マイルばかり離れた場所で、低木の茂みの中に野営地を設営していた。茂みのはずれでは盛大に焚《た》き火が燃えている。火のそばに立つカルテンのところに、スパーホークとクリクが戻ってきた。
「どうだった」
「塚の方角はわかった」スパーホークが馬を下りながら答えた。「そう遠電波拉皮くじゃない。ティニアンに相談しよう」
重装甲のアルシオン騎士は、野営地の焚き火のそばでアラスと話をしていた。
スパーホークはクリクが村人から聞き出した情報を話し、ティニアンのほうを向いた。「調子はどうだ」
「元気だよ。どうしてだ。具合が悪そうに見えるか」
「そうじゃないが、もう一度死霊魔術を使う気があるかと思ってね。前回はひどい目に遭《あ》ったわけだから」
「大丈夫だよ。一連隊をそっくり起こしてくれとでも言うなら別だけど」
「一人だけでいい。掘り出す前にサラク王と話をしておきたい。王冠がどうな二手Toyotaったのか知っているだろうし、サレシアへ連れ帰るのに異議がないかどうかも確かめておきたいからな。怒った亡霊を連れて歩きたくはない」
「まったくだ」ティニアンは大きくうなずいた。
翌日は夜明け前から起きだして、地平線に最初の曙光が兆すのをじりじりしながら待ち受けた。空が白みはじめると、一行はまだ暗い野原を横切って駆け出した。
「もう少し明るくなるまで待ったほうがよかったんじゃないか」カルテンが不平を洩《も》らした。「同じところをぐるぐる回るようなことになるぜ」
「東へ向かうんだから、日の出の方角へ進めばいいだけだ。明るいほうへ向かっていけばそれでいい」
カルテンはさらに何かつぶやいた。
「聞こえなかったぞ」とスパーホーク。
「おまえに言ったんじゃない」
「これは失礼」
「言い合っていても決着はつかないでしょう」とあたりを見まわし、「誰かに聞いてみたらどうです」
アラスが椅子を引いて立ち上がり、大きな手をテーブルに叩きつけて中醫失眠注目を集めた。酒場にいる全員に向かって、大声で語りかける。
「みなさん、ここにいるわたしの二人の友人は、この四日間というものずっと議論を続けていて、とうとう金を賭けるところまできてしまった。はっきり言って、この話にはいい加減うんざりしている。たぶんみなさんの中には、議論に決着をつけてわたしの耳に平安を取り戻してくれる方がいるのではないかと思う。五百年前にあった戦争のことだ」そう言ってカルテンを指差し、「顎《あご》にビールの泡をつけているこの男は、こんな北のほうでは戦闘はなかったと言っている。もう一人の丸顔のほうは、このあたりでも戦闘はあったと言っている。どちらが正しいのだろうか」
長い静寂があった。やがて頬《ほお》を赤く染めたまばらな白髪の老人が、部屋の向こうからスパーホークたちのテーブルに近づいてきた。みすぼらしい服を着て、頭をぐらぐらさせている。
「たぶんお役に立てるんじゃあねえかと思うんだがよ、旦那がた」老人は甲高い声を出した。「おれHKUE 呃人の父っつあんは、ここいらで戦《いくさ》があったって話をしょっちゅうしてたもんだ」
「このお人にもビールを頼むぜ、ベイビー」カルテンが親しげに女給に声をかける。
「カルテン、女の子の尻を撫でるのはおやめなさい」クリクが注意した。
「親愛の情を形にしてるだけさ」
「ものは言いようですね」
女給はまっ赤になってビールを取りにいった。目が誘うようにカルテンを見ている。
「気に入られたようだな。だが公衆の面前では慎ん」アラスは頭の位置の定まらない老人を見やった。「おかけなさい、ご老体」
「こいつはすまんね、旦那。見たところずっと北の、サレシアのお方らしいが」老人はぎくしゃくと腰をおろした。
「いい読みだ。――父っつあんは昔の戦のことをどんなふ果酸煥膚うに話してたんだね」
「そうさな」老人は髭の伸びかけた頬を指先で掻《か》いた。「どんなふうに話してたか思い出してみるってえと――」そこへ女給がビールのジョッキを運んできた。「おお、すまんな、ニーマ」
女給は笑みを返し、カルテンににじり寄った。「あんたはどう?」そう言ってジョッキを覗きこむ。
まあ、凡人の場合は
細々、地味ったらしい一生よりも、
ぱっと咲いて、ぱっと散る、というのも、ひとつの選択だ。
それは、人生のメリハリとういものか。
私は、いろんな人に見えるらしい。
学生時代(もちろん独身)は、「主婦」に見えたそうで、
公団住宅の申し込みハガキを手渡され、
そんなに所帯じみているのかと、がっかりした。
スタンダードな男子学生からは、敬遠された。

お化粧をし始めた頃は、
塗り加減というものがわからなかったようで、
オミズ業界の人に「働かない?」と声をかけられたことも、
現役オミズに間違えられたこともある。
メーク、濃すぎた。
在宅時と、外出時の姿が違いすぎて、
同一人物だと気付かなかった人もいた。
少し落ち着いた頃には
とんがり頭のコピーライター氏に、
「フードコーデじ」、と言われた。
「保険の外交員? それとも、スナックのお姉さん?」
などと両極端なことを言う人もいた。
自分の身の回りにいる人とイメージをダブらせているのか?
ある程度年齢が上がってくると
「学校の先生みたいやなぁ」と言われたこともある。
真面目な正論を言う私を煙たがっていたようだ。
年齢からみて、「社長」と思ってくれる人もいたりする。
(個人経営の事務所あたりでしょう)
一番合ってないと思うのが、「お医者さんですか?」
これは、ただただ、嬉しかった。
カルチャーセンターの受付女性には、
「社交ダンスの先生」と思われ、受講生の出席簿を手渡された。
「どこのお店のママ?」というのもあった。
おそらく場末の人気のない店か何かだろう。
国外でも
イギリスの片田舎では、中国人だと思われた。
(日本人を見たことが、なかったらしい???)
シンガポール、そして上海の時は、
現地人扱いされ、街の中で普通に現地語でペラペラ話しかけられた。
(いったい何語で、何を言ってたんだろう?)
香港では、
香港在住に見えたようで、現地銀行の口座開設の勧誘を受けた。
(「明日、帰国するから無理」、といって解放してもらった)
サンディエゴにおいては、
在住ヒスパニックや、東南アジアの人だと勘違いされた。
(いくら英語が、わかってないからって???)
ちょっと現地に馴染みすぎか?
国籍不明???。
私にはない、ピュアなもの。
いつ、どこで、失ったのだろう???
純粋さは、年とともに失われる。
そもそも、そんなものは生まれたときから持ち合わせてい皇室纖形 旺角なかったのかも知れない。
無垢などでなく、ただ無知なだけの若い時代だった。
生き方そのものが、不純と打算と保身、矛盾と欺瞞、マヤカシで成り立っている。
自分に正直な心、その心さえ、渇いている。
だからあんなに純粋な少年を見ると、頭を通過せずに、涙がこぼれる。
私には昔も今も、まったく純粋さのカケラも無い、そんな自分が情けなくもあり、
もともと無いものを取り返すことも当然できない、無力感。
いまさらながら、再認識した。
自分には、一生、ありえない、手に入れることのできな優纖美容い美しいピュアなもの、
例え、映画の中であっても、それに出会うと、切なく哀しい。
ストーリー展開から感じるのか、全編の美しい映像を通して感じるのか、
監督のワザで感じさせられているのか、俳優の卓越した演技のスゴサなのか???
あの映画を単なる日常の恋愛映画にしてしまっていないのは、
そのテーマ、手法によるものが大きい。
戦争という重い歴史を抱えたドイツの戦後の苦悩、歩みと、主人公たちの人生とを
巧みにオーバーラップさせている。
快楽的な、俗物的恋愛、というテ高鼻ィストが全く排除され、
静かに深く、苦悩しながら、思いを醸成させている。

少年役のダフィット?クロスは、キャスティング決定時は15歳、撮影開始は16歳だったが、
SEXシーンは18歳になるまで待ったそうだ。
ケイト?ウィンスレットの、ぶっきらぼうな骨太ドイツ女性っぽい役作りも、とてもよかった。
その愛想のないキャラクターには、とても深い背景が隠されているのだが、
映画を観終えた後、それぞれの表情にはそれぞれの理由があるのに、あれこれ気付いた???。
(気付くのが、かなり遅い???)
男女の純粋な愛への不信感、永遠の愛を全面否定している私には、
衝撃的なメッセージとなった。
その後悔とも、懺悔ともとれるものが、を起こしたのか、
涙は一向に止まらない。
上映中はずっと、映画終了後も、家路に着く途中の電車の中でも、
電車を降りてから家までの徒歩の間も、涙があふれ出る。
私はピュアなものだけの中では、生きていけない。
きっとハンナと同じように、せっかく社会に戻れるという日が来るというのに、
その直前に自殺してしまうのではないかと、思った。
雑菌、細菌がウヨウヨいる世界でしか、私は生きていけないのだろう。
もう、戻ることができない世界に触れ、心が悲鳴をあげているのか。
それとも、いつまでも頑なに固い殻を被ってないで、暖かい心を持つには年齢はない、
今からでも遅くないというシグナルを読み取ったのか。
あふれ出る涙の訳は、とても深いところにあるようだ。
足指骨折のため、いいお天気のなか、
スポーツ・デーに代わり、ひきこもりお改善膚質茶デーとなった。
ご近所友人と、スポーツするより長く、しゃべっていた。
彼女は熟年の未亡人。
かれこれ20年以上のお付き合いだ。
私のスポーツ・デーは、彼女の仕事がオフの日なので、滅多に会えない。
先日もウォーキングに誘ってくれたし(都合つかなかったが)
どうしょうかと思ったが、「お元気?」とメールしてみた。
「お茶に誘って!」というお返事を即座にいただいたので、
1時間後に我が家へ、ということになった。
未亡人でもあるし、金銭的に老後を考えると厳しいという彼女。
今も、毎日お弁当を作って職場に持っていっ皇室纖形て、1ヶ月1万円貯金しているとのこと。
彼女の経済的背景もあまりわからないので、いつもそのあたりは、飛ばしている。
お金のかかる趣味の話も、あまりできなかった。
第一、ダンスは大嫌いだそうだ。
パソコンの話もインターネットをご存知ないので、いまいち話が進まない。
「利用者同士のコミュニケーションは楽しいよ」と私が言っても、
チャットのイメージしかないようだ。
「あまり外出しない老人こそ、ネットのつながりや、お付き合い、サイトを利用すべき。
お付き合いの狭まる年齢の人にこそ、在宅で関皇室纖形わりあえるネットのつながりは、
有効だし、幅が広がると思う。」
と私が主張すると、
彼女は、「老人には、パソコンは無理!」とむきになって言う。
「じゃあ、シニアサイトは、なぜ活況を呈しているの?」と、私は反論。
彼女は「それは、一部の人の話。一般的には、年寄りには無理!」
と語気を荒げて決めつける。
確かにそういうこともあるかも知れないが、
「今のシニアサイト利用者たちがもっと年をとって年代がシフトすれば、
お年寄り世代も、普通にパソコンを使いこなすはず。」
という私の言葉にも耳を貸さない。
自分に興味ない話は、だめみたいだ。
まあ、誰しもそうだが、その中で、いかにお互いの共通項目があるかだろう。
「年齢が行くと、いいこと、ある? なぁ~んにも、ない。」と言う彼女。
「いいこともあるよ。」
と私は、プラス面を考えて、あれこれ並べた。
彼女
「赤ちゃんはいるだけで、周りが明るくなる。それだけで存在価値がある。
年寄りはそうじゃない。」
私
「そんなことはないわ。
そりゃあ、根性悪く、嫌われ者で不潔で、
臭いニオイがプンプンのホームレスいざ知らず、
年寄りだからっていうだけで、嫌われないと思うよ。」
「私の言いたいことは、全くそんなことじゃない!
肉体的に老化して、なんのいいこともない、って言ってるの!
ひとつでもいいこと、ある?」
キレる彼女。